
パノラマ座談会「古い焼きものに想いを寄せて」 後編 1/3 森 由美 (陶磁研究家、戸栗美術館・学芸顧問) × 浜野マユミ (陶芸家) × 吉永サダム (陶芸家) × 矢野直人 (陶芸家)

森 由美
陶磁研究家。
戸栗美術館学芸顧問。
東京藝術大学大学院美術研究科(保存科学専攻)修了。
戸栗美術館学芸員、日本陶磁協会研究員を経て独立。
著書『古伊万里との対話』(淡交社)『週刊やきものを楽しむ・全30巻(兼・監修)』(小学館)等。(筆名・中島由美)

浜野マユミ
1974年埼玉県川越市生まれ。
武蔵野美術大学日本画学科卒業後、佐賀県立有田窯業大学校進学。
伝統工芸士 秀島和海氏、李荘窯 寺内信二氏に師事。
2001年川越にて開窯。
4年間休業し、2013年作陶再開。

吉永サダム
1975年伊万里市生まれ。
龍谷大学卒業後、佐賀県立有田窯業大学校進学。
卒業後、嘱託講師として2年勤務。
その後、佐賀県嬉野市「風ン谷淳窯」野村淳二氏に師事。
2006年より伊万里市の自宅工房にて独立。

矢野直人
1976年唐津市生まれ。
5年間のアメリカ留学後、佐賀県立有田窯業大学校進学。
卒業後、嘱託講師として勤務。
2004年より自宅殿山窯にて作陶始める。
2008年韓国蔚山にて6カ月作陶。
人間味を宿す磁器の美しさ
森 窯業大学校卒の皆さんが、揃って古い焼きものを熱心にご覧になっているというのは、偶然でしょうか? 陶芸をされている方が皆さんそうではないし、自分の造形をしたいということでこの道に入られる方も大勢いらっしゃる中で、窯業大学校というのは、そういう古いものの技法とか土とかへのこだわりが生まれるような授業なり背景があるのでしょうか。
矢野 授業からは感じないですが、地理的なことは関係あるかもしれません。たとえば関東から関西へ向かってきて、備前の作家さんくらいまでは、今の感性に近いけれど、より西へ行くにつれて、唐津とかはそこが薄れて行くような気が僕はします。町の暮らしのおしゃれな感覚が薄れて行くというか。とくに唐津は素材感のすごく豊富なところなので、古いものとか素材へのこだわりを持つ人が生まれやすいとも思います。それとタイミング的に、僕の上の世代の唐津の作家さんたちが、新しいことをやっている人たちが何人かいて、その影響はあります。素材だけじゃなくて、物をより求めるというところなど。なので、浜野さんが糸切でやるというのも、自分にはリンクしやすかったです。
吉永 僕らの世代だからというのはあるのかもしれませんね。唐津だと、土もので薪とか歪みとかで面白いもの、美しいものってあるんですけれど、磁器でそういうのって今はなかなか受け入れられなくなっている感じがするんです。衛生的過ぎるというか、工業製品的なものが溢れていて、でも昔の江戸の磁器とか残っているものを見ると、今のものと比べてそんなにきれいじゃないし、ちょっと鉄粉があったりするのもある。でも美しいとされて残っている。そこは僕とリンクする感じがあって、もうそれでいいんじゃないのって。きれいなだけじゃない美しさというのは芯があると思うんだけれど、そこって今の時代に何か見失われているという気がして、僕はそこをやりたいと思いました。
 色絵 梅花丸文 分銅形皿 伊万里(古九谷様式)江戸時代(17世紀中期)/戸栗美術館 2階 第一展示室
色絵 梅花丸文 分銅形皿 伊万里(古九谷様式)江戸時代(17世紀中期)/戸栗美術館 2階 第一展示室
浜野 有田には、古伊万里の美術館も多いですし、九州陶磁文化館の柴田コレクションのように、古いもののいいものが身近にあって、そういう影響も大きかったと思います。私は、多くのことを柴田コレクションから学びました。器から陶工の性格や時代背景が見えるような気がします。鍋島のものを見て感じるのと、初期伊万里のものを見て感じるのと、それぞれに良さがあって。人間性がその器に入っていて、そこに感動するような気がするんですね。それは磁器でも陶器でも何でもいいのかもしれない。
森 浜野さんの好きな焼きものは、17世紀中期から後半にかけての辺り。
浜野 はい。いいなと思うと、だいたい1650年代と言われている辺りですね。もしかするとその時代が好きなのかなとも思います。その頃の有田に住んでいた人とか。
森 吉永さんが好きなのは、初期伊万里になりますか。
吉永 やっぱり初期の頃の人間臭さというか、そういうのが匂う器ですね。浜野さんの好きな時代もいいなと思いますけれど、僕が今興味あるのは白磁なので、いちばん裸というか、素材と釉薬と焼きで見せていく感じですね。プラス造形もありますが。
 白磁鎬文小坏 柴田夫妻コレクション(6-90)/佐賀県立九州陶磁文化館柴田夫妻コレクション(国登録有形文化財)
白磁鎬文小坏 柴田夫妻コレクション(6-90)/佐賀県立九州陶磁文化館柴田夫妻コレクション(国登録有形文化財)
浜野
私は初期のものは、何となくソワソワする感じがあって、しっくりくる感じというのは、やっぱり人それぞれだなと思います。
矢野君は出光美術館*12で見た唐津が、探究のきっかけなんですよね。
森 古唐津の展覧会の時ですか。具体的にはどの作品になりますか。
矢野
「さざれ石」*13です。そういうのは、ヒゲ生えたおっちゃんみたいな人が、私はこれを見て人生変わったよとか言いそうなので、あまり言いたくないんですが、実は僕もなんです(笑)。唐津焼は父もやっていて、それがいいとか悪いとかではなく、だいたいの唐津のイメージというのはあったんですけれど、まったく別物に感じたのはやっぱりこの作品ですね。
それまで30歳頃までは、どちらかというと造形的な作品の加守田章二さん*14や肥沼美智雄さん*15、和太守卑良さん*16とかに憧れがありました。ただ、そういうものに一生懸命になれば、よりそれを見るようになるし、いざ自分でつくると、その人の真似じゃないの?みたいなことで、それが自分の中では腑に落ちなかった。そんな時に、古いものを見て感動して、そこに近づく作業というのは、ある意味評価されることでもあって。産地の作家として、そういうのは自分の中では心地いいというか、やりやすいというか、すんなり仕事ができることでもあります。
森 ちょうど皆さんのそれぞれ好きなものが、年代でつながっていますね。唐津焼があって、そこから磁器が誕生して、磁器の技術が完成して行ってという、ちょうどその流れで関わっていらっしゃる。
吉永 歴史の流れ通りですね。朝鮮から唐津に技術が入ってきて、そこから有田に広まったわけですが、技術的には唐津から始まった日本の技術革命が、有田で花開いたという形ですよね。つながっているからか、何か想いも共通するものがあるような気がします。
浜野 面白いなと思うのは、矢野君は唐津の海に面したところに住んでいて、大自然に囲まれている。有田までも車で1時間くらいかかりますよね。私は首都圏で育って、子どもの頃、沢蟹を採りに行こうとなると1時間くらいかかるようなところ。今も私は横浜のマンションに暮らしているし、矢野君は目の前に海が広がっていて。だから私と矢野君の環境は真逆なんですね。でも会うと、興味を感じるところは共通していて、そこが面白いなと思います。吉永君はその中間ですね(笑)。
吉永 工房に沢蟹も来るしね(笑)。
*12:出光美術館
出光興産の創業者・出光佐三氏の蒐集した出光コレクションを展示するため1966年に創設された美術館。東京・丸の内の帝劇ビル9階にある。日本と中国の書画、陶磁器など東洋古美術が中心。アジアや中近東の遺跡、窯跡から出土した陶片資料を集めた陶片室もある。また2000年に福岡・門司港にも美術館を開館。
*13:さざれ石
松浦家伝来「奥高麗茶碗 銘 さざれ石」出光美術館蔵。桃山時代の古唐津。奥高麗茶碗は茶道具の最高峰とされる。
*14:加守田章二
1933‐1983 大阪生まれ。京都市立美術大学工芸科陶磁専攻卒。富本憲吉氏や近藤悠三氏の指導を受けた。日立製作所の社員として茨城県日立市の大甕陶苑や栃木県益子町の塚本製陶所に勤めた後、益子にて築窯、独立。その後、岩手県遠野に築窯。
*15:肥沼美智雄
1936年、東京生まれ。大阪大学経済学部、早稲田大学政経学部中退。栃木県益子町に築窯、独立。益子町在住。
*16:和太守卑良
1944‐2008 兵庫県生まれ。京都市立美術大学工芸科陶磁専攻卒。高知県安芸市にて作陶を始めた後、茨城県笠間市に移住した。
浜野マユミ作品展
「戸栗美術館 1階やきもの展示室」にて、浜野マユミ氏による作品展を開催致します。
古伊万里の伝統技法を用いて、日本の四季を表現した小皿・猪口などを展示。
制作に用いた道具類もご紹介します。
企画展「小さな伊万里焼展 ―小皿・猪口・向付―」とあわせてお楽しみくださいませ。
財団法人 戸栗美術館[東京渋谷・陶磁器美術館]
〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-11-3
tel. 03-3465-0070
http://www.toguri-museum.or.jp
» Report 浜野マユミ作品展@戸栗美術館
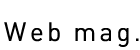


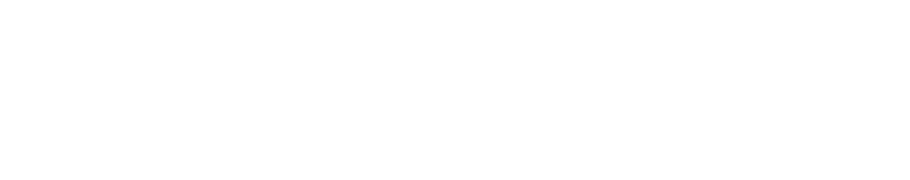 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net