
木の木口に楔をいれ木目に沿って割り裂く、「へぎ」と呼ばれる木工技法によって、工藤茂喜さんの作品は作り出される。おそらく知る人は稀であろう「へぎ」という技法、それによって生み出される工藤作品の魅力について解き明かしてみたい。作家である工藤茂喜さん、プロデューサーである井上典子さんに語っていただこう。
-
「へぎ」とは、
木を加工するための、
一番プリミティブな技法。
-
——
「へぎ」という技法について、耳慣れない人も多いと思います。まずはその技法について、歴史を交えてお話いただけますか?工藤
「へぎ」というのは、ノコギリなどの道具が発達する以前からあった木工の技術なんです。木を割る、つまり原木を加工する一番シンプルな技法だと思います。たとえば落雷が立木を割り裂く様子、そうした自然現象を偶然に見たことが、技法として発達するきっかけになったのかもしれない。ごく初期段階に発生した技法で、その基本は今もほとんど変わっていませんね。井上
木工における最もプリミティブな技法で原点みたいなものなのに、その割には、一般的に知られていないですね。工藤
角偉三郎※1さんは「へぎ」で作品を作られていましたね。井上
実は、私の最初のへぎ体験は角偉三郎さんなんです。かつて角さんの個展で、ものすごく大きなへぎ板が一枚、どーんと会場に展示してあるのをみました。それがへぎの卓だったんです。その後、輪島に行ったら、木地屋さんの家の外にそのへぎ板が材料として立てかけてあったんです。素材としてとても面白いと思い、ギャラリーを始めるとき、「へぎ」もやってみたい、と思いました。とはいえ、角偉三郎さん以外に「へぎ」をやる人が居るのかどうかも分からなかったのですが。工藤さんが初めてギャラリー介※2にみえて「へぎでやりたい」とおっしゃった時、作品見本もなかったのに即答したのにはそういう背景があったのです。
-
——
へぎという技法は、本来どういうところで使われたものでしょうか。家具に使う、器に使うなど、具体的な用途という意味ですが。工藤
「へぎ」とは言わないかもしれませんが、まず第一に浮かぶのが建築の梁です。井上
なるほど、そうですね。工藤
ノコギリを使う前の時代は、楔(くさび)を入れて木を割り裂いている。特に五重塔など古い建築にはよく出てきます。木の皮をはぐことも「へぎ」という技法の一例です。「へぐ」という動詞を名詞形にすると「へぎ」になる。「へぐ」というのは「剥ぐ、剥がす」の派生なんじゃないかな。井上
家具や器にはあまり使われてないでしょ?工藤
ギャラリー介※2で個展をした時にお客さんから聞いた話ですが、伊勢にお参りに行ったとき、たまたま行われていた神事を見ていたら、杉のへぎ板に供え物を並べていたそうです。井上
お皿の原点ということですね。土器よりも古いのかしら?工藤
古いと思いますよ。木を割り裂いて使うというのは、かなり古くから自然発生的にあったんじゃないでしょうか。井上
ノコギリやカンナなどの道具が発展するにつれ、へぐ、という技法が一般的ではなくなった。けれど、そういった流れの中にあって、仏像造りではあえて「へぎ」の技法が使われていた……。その仏像造りの工程を目にしたことが、工藤さんを「へぎ」へ結びつけるきっかけともなりましたね。 -
剥ぐ、剥がすという動詞を
名詞にすると、「へぎ」になる。
-
吸い付くように、
ぴたりと合わさる。
それが心地よい。
-
工藤
僕は芸大の漆芸科出身で、以前は塗りの椀などを展覧会に出していました。「へぎ」を始めたのは2001年ぐらいからで、当時、仏像修復に携わる友人を手伝うために、芸大の地下にあった仏像修復の工房に出入りしたことがあったんです。そこで、二つに割り裂いて中がくり抜いてある仏像の頭を見たんですね。
不思議に思って「なんでこれ、割ってくり抜いてあるの?」って聞いたら、無垢のままだとヒビが入っちゃうので中をくり抜くんだ、って言うんです。ノコギリで切るとその線が徐々に目立ってきて狂いが生じるけど、割り裂いたものを戻して漆で接着すると継ぎ目が跡形もなくなる。そう聞いたんです。
漆を習う段階で何度か目にはしていましたが、「へぎ」という技法を面白いと思ったのはこの時がはじめて。割って、くり抜いて、戻す。これは何か、工芸的な入れ物にも使えるんじゃないか、そう思ったのが始まりですね。井上
そういう発想に繋がるところが工藤さんの面白いところ。誰しもそうは思わないでしょう。工藤
井上さんが最初に僕の作品をみた時と同じ感動がそこにあったんです。吸い付くようにぴたりと合わさる。触らせてもらったら、「ああ、ほんとだ」って。木の導管に沿って裂いているので接着面に隙間がないんです。それは仏像彫刻の人にとっては当たり前のことだったんですけど、僕にとっては新鮮な驚きだった。井上
あのピタッと吸い付く感じが、なんとも言えなくいいですね!はじめて工藤さんの「へぎ箱」を見たときにはびっくりしました。それまでは角偉三郎さんの「へぎ板」しか知らなかったから。
-
工藤
工芸の場合「へぎ」という技法で割り裂くことはあったけど、"割り戻す"ということはやっていなかったんですね。みんな、へいだ板の片割れを単体として作品にしていたから。あとは建材として薄く剥いだへぎ板を天井の網代組につかうことはありますけど。井上
いずれにしろ、「へぎ」という技法はあまりメジャーな世界では使われてこなかったということですね。工藤
どちらかというと技術というのは、同じ物をそっくり複製するために進化するものだと思うんです。つまり、人間の手が作ったのに、工業製品的な精度に肉薄するワザが珍重された。たとえば、揃いの蒔絵の椀が五つあるとすれば、それを寸分違わず同じ模様と筆致と艶に作ることが最良とされていた、ということですね。逆に「へぎ」の場合、同じ物は絶対に出来ないから、均一な精度を求める発想とは逆に、他と違う事に意味を求める方向に行ったのだと思います。 -

-
同じ物を複製するために
進化したものが技術。
その真逆にあるのが「へぎ」。
-
井上
なるほど。同じ物を複製するために進化してきたのが技術、これは名言ですね。その真逆に「へぎ」はあるということですね。工藤
どの分野でも職人技といえばそうでしょ? たとえば陶器なんかも、ロクロで挽いたとき、ぴったり同じ大きさの揃いで作れる。それが職人のワザでしょう。逆に縄文土器みたいにプリミティブな物は、ぴったり同じになんて出来ない。物作りの歴史を振り返る時、いかに精度を持って作るかということが人々にとっての悲願であり、祈りでもあったんじゃないでしょうか。井上
「へぎ」というのは、ある意味すごく原始的な技法ではあるけど、原始的であればこその力がありますよね。どんな風に世の中が変わっても残っていく技法であると思う。工藤さんから見て、この先「へぎ」という技法はどう変わっていくと思いますか?この先世の中に拡がりますか?工藤
技法が拡がるかどうかは、僕はあまり気にしてはいません。
※1:角偉三郎(1940~2005)
漆芸家。石川県輪島生まれ。15歳で沈金の修業を始め、パネルに絵を描く作品で次々公募展に入選し38歳で日展の特選を受賞する。しかし2年後、一切の公募展から退く。以後、蒔絵や沈金といった加飾を離れ、ざっくりとした、普段使いの器の制作に変わる。
きっかけは輪島の隣町で作られていたと言う、古い椀(合鹿椀)を骨董屋で手に入れた事がきっかけと言われている。
当時、産地は美しい塗りや加飾に高い価値を置いていたが、気兼ねなく使える器の出現は、良質の普段使いの漆器を求めていた客に、圧倒的に支持された。へぎ板を使った作品も制作していた。
亡くなった今も、角工房の作品の人気は高い。
※2:ギャラリー介
2000年4月~2008年6月まで、渋谷区東にあったギャラリー。ガラス、陶、木、金属、布など幅広いジャンルの作家の作品展を開催。井上が運営。

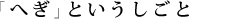


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net