
-
歴史とも産地とも
関わりがなく、
伝え残す技術でもない。
-
井上
木工の世界の本流とは?羽生
わかりやすく言えば伝統工芸とか、クラシック~モダンの家具づくりというのが本流とされるんじゃないですか。僕の木工は、歴史とも産地とも関係がないし、残す技術でもない。たぶん一瞬世に出て、そのうち消えていい家具なのかなと。井上
そういうご自分の立ち位置というのは、工業デザイナーから転身して木工をスタートしたことと関係ありますか?羽生
かなり肌で感じています。こういうものをつくるべきっていう発想ができなくて、何ができるだろうっていう発想に、ついなってしまう。まず、こういう家具をつくりたいという憧れのものがない。いいと思ったものを僕もつくってみようとは思わないんです。たとえば、ウェグナー※9がいいと思ったら、それは買うべきと考えてしまう。井上
それを超えるものをつくろうではなくて?羽生
やる前から、超えられないなと。その方にお任せするべきかなと。井上
そう考えるのは、工業デザイナーをしていたことと関係ありますか?羽生
ウェグナーみたいな仕事をするとなると、僕はデザイナーとして参加した方がいいんですよ。自分の技術レベルもあるけれど、いい工場や職人がやっていくもので、一人でつくるのには向いていないというか、中途半端になってしまう。結果を望むなら、デザイナーの方がいいと思う。井上
デザイナーをやめて、一人でつくることをしたかった?羽生
デザイナーはユーザーやマーケットを設定するんですけど、その能力は僕にはない。すると、自分が欲しいかどうか、という方に行く。つまり、マーケットにはずれたつくり方をするには、一人の方が身動きとりやすいってことです。工業デザイナーは責任の所在が広すぎて、何か一つ売れないと、その責任はデザイナー個人ではとれなくて、営業や製造の人々を巻き込んでしまう。その責任の中で、僕は売れなくてもこのデザインをやりたいとは、なかなか言えなかった。だったら一人でつくる方が、責任は自分の家族くらいで済むから気楽ではありますね。
-
井上
先日、銀座の「日々」※10さんで行われた羽生さんの個展を拝見して、工業デザイナーをされていたことが、いい形で今に結びついたなと感じました。羽生
実は、自分の中の禁を解いたんです(笑)。井上
作家活動を始めた頃からずっと、木の器と家具をつくり続けられていますが、器は別にして、家具は少しずつ変わってきているでしょう。羽生
福島の頃、最初はつくりたいものがはっきりとなくて、でもモヤモヤしていて。何かをつくっては、これはダメ、という消去法で模索していた時期があったんです。その時期は、まだ自分の中に工業デザイナー的思考が残っていて、そこに頼ってしまう。でも、そういうつくり方はしない方がいいと思って、その考え方を自分から追い出すというか、封印するまでに2年くらいかかりました。そこから、クラフト展で賞をいただいたものが、ようやくつくれるようになったんです。そして十何年かやってきた今、一区切りというか、余裕が出てきて、工業デザイン的なものを出せる時期になりました。これまで禁止していたんです、ずっと。 -
自分の中の禁を解いて
デザイン的な家具も
つくり始めた。
-
もののかもし出す
空気みたいなものに
こだわりがある。
-
井上
ある時期から、素材として金属も登場していますね。羽生
店舗の仕事を頼まれたことがきっかけだったと思いますが、木より鉄の方が、繊細さを表現できる。空気感とか、佇まいみたいなものです。井上
脚部のこの細さを木では実現できないですものね、物理的に。羽生
初めは繊細さが欲しかった。今は、繊細さを出し過ぎてもよくないと思っています。井上
でも、初期のグランプリを受賞した頃の作品は、繊細ではないのでは?羽生
僕には、あれも重くはないんです。井上
確かに重量感はないけれど、存在感があったでしょう。その存在感やプロポーションにとにかく驚きました。そしてテクスチャーがすごく面白かった。羽生
昔から、ものの周りの空気みたいなものに、すごくこだわっているのかもしれない。井上
なるほど! それはすごくよくわかります。初期の作品も、今の作品も、 どちらもそこに羽生さんを感じますね。
※9:ハンス・J・ウェグナー
20世紀の北欧デザインを代表する、デンマークの家具デザイナー。
「チャイニーズ・チェア」「ピーコック・チェア」「ザ・チェア」「Yチェア」など数多くの名作椅子を手がけた。
※10:日々
「エポカ ザ ショップ銀座」の地下1階にあるギャラリー。

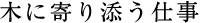


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net