
「やわらかい」。井上典子さんは、高橋禎彦さんのガラスをそう言い表す。「冷たくてカタイ」、そんなガラスのイメージを軽々とひっくり返してしまう、しなやかな力の秘密は、もしかしたら作品以上にやわらかくてユニークな、高橋さん自身のキャラクターにあるのかもしれない。ガラスアーティスト高橋禎彦さんの魅力に迫るのは、プロデューサーの井上典子さん。二人の熱いライブトークをお楽しみください。
-
日本にこんな人がいた!
初めて作品を見た時、
衝撃を受けました。
-
——
まずは、井上さんと高橋作品の出会いからお話いただけますか?井上
私が高橋さんの作品を最初に見たのは多分1986年頃です。高橋
86年というと、個展を始めるようになって1年目ぐらいですね。井上
私は1960年代後半から主にインテリア、リビング関係の仕事をしてました。その頃からガラスに興味がありましたが、当時はスカンジナビアデザインの全盛期で、日本の作家の面白い作品に出会う事は殆どありませんでした。その後80年の初めからフリーで仕事をするようになり、ある時、高橋さんの作品を見て、「日本にこんな人がいたんだ!」と衝撃を受けたのです。高橋
ありがとうございます。その当時は昭和的なことに対して、色々な意味でイヤでした。モダンになりそこなった日本、がもどかしく見えたのかもしれない。今でこそ、そこが面白かったりするんだけど。
-
井上
その時代、日本ではガラス作家という存在は少なかったですね。高橋
当時僕にとって、一番刺激的だったのはアメリカの作家。特に80年代までは面白い展開があったように思う。理屈じゃなくて、何かかっこよかった。たぶん、そのころはアメリカのガラス作品が一番盛り上がっていた時代だったんじゃないかな。——
高橋さんは早い時期にドイツへ渡っていますね。高橋
アメリカやヨーロッパと日本の違いって何だろう? そういう疑問が僕の出発点にありました。日本というのは自分が生まれ育った国であるわけだし、その内側にいるだけだと見えないことだらけなはずです。それを外側から眺めて対象化してみたくて、外国に行ってみようと考えました。日本の枠を超えるにはどんなアプローチがあるのか、そういった勉強って学校ではできなかったから。井上
学校といえば、高橋さんは多摩美の出身ですけど、最初からガラスの専攻でしたか?高橋
当時多摩美に工芸科はまだありませんでした。立体デザイン科というのが良さそうな気がして、何をするのか全く知らないまま入りました。学校へ行くと隣の席のやつが机でイタズラ書きをしていて、それが車のレンダリング※1みたいな絵だったのね。それを見て、「ああ、俺は違うところに来ちゃったな」って初めて気付きました(笑)。そうしたら3年生から、ガラスコースに移る機会ができて……井上
その頃に工芸科が出来た?高橋
僕が1年生の時に出来たんです。3年生の時には窯も出来てた。 -
80年代、
アメリカのガラスには、
理屈じゃない、
カッコよさがあった。
-
当時、
海外作家のガラスは、
音楽でいえば、
クラシックじゃなくて、
ジャズみたいな感じ。 -
井上
それで、ガラス科に行ってみて面白かったですか?高橋
ガラスを吹くのも面白かったけど、最初の年に京都でWCC世界クラフト会議というのに行く機会が出来て、海外の作家がスライドを使って自分の作品や制作の歴史について話すのを見たんです。ガラスを使ってみんなが面白いことをいろいろやっていたのを見ました。そういうのがいわゆる伝統的な工芸ってやつとは違って見えて、カッコいいワケは何なんだろう? って考えた。音楽でいえば、クラシック的じゃなくてジャズみたいな感じのアプローチ。井上
その当時日本には、伝統工芸的なものづくりをする作家はいても、それ以外の作家はいなかったのでは?高橋
ヨーロッパにはいたけど、日本にはまだいなかった。じゃあ、伝統技法ってなに? っていうと、綿々と長い時間をかけて理由がわからないぐらい洗練されてきちゃった技術なんだと思う。でも、その時に見たリアルタイムなガラスは、もっとわかりやすくて、直接心にグッと来る感じ。ジャンルに関係なく、そういう世界がWCCに来ていた作家達にはあった。それが一番大きな発見だったんじゃないかな。
※1:レンダリング
数値データの情報を物体や図形に画像化すること。

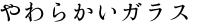


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net