
-
井上
私は毎回、工藤さんの新しい作品を見る度に新鮮な驚きを感じるんですけど、第三者としては、この「へぎ」という技法を使ってまた違った作品をつくる作家が出ても面白いのにな、って思っているんです。工藤
ああ、それは僕にとっても面白いですね。技法も秘伝というわけじゃなし、常にオープンですから(笑)。でも、秘伝って言われる物って、すぐ真似できるから秘伝にしているんですよね。レシピがあれば作れる秘伝のタレみたいなもの?井上
そうか、真似できちゃうから秘伝にするわけだ(笑)。 -

-
自分の漆芸の核に
木工があるから
外した漆の使い方が出来る。
-
井上
話は戻りますが、工藤さんは芸大の漆芸科専攻ですが、漆を選んだきっかけは?工藤
子供の時から木で工作するのが好きだったんです。とにかく、数ある素材の中で、木という素材が好きだった。ところがそのころ芸大には木工科というのが無かったんです。それで使う素材として木のウエイトが高い漆芸科を選択しましたが、今となっては漆をやっておいて良かったと思っています。井上
それはどういう意味で?工藤
木工がずっと核としてあり、そこにどのように漆を取り入れるかという発想ができたからだと思います。漆を学んだからこそ、伝統的な方法以外に、外した使い方も出来るようになったと。井上
漆器業界では塗と蒔絵が最高峰という意識がありますね。最近は変わってきてるようですが。工藤
漆の場合はそうですね。行程が多くて手間が掛かりますから、しょうがない流れかもしれません。井上
私は、塗り込める事が絶対的な価値だとは思えないのです。だから、木地そのものを活かした工藤さんの作品が好きなんだと思います。
-
工藤
僕がよく使う技法、これなんかもそうですが、漆の行程でいうと下地で終わっているんですよ。漆の人なら絶対こんなことしないですね(笑)。井上
たとえばこれは、どういう行程になるんですか?工藤
まず最初は拭き漆といって、生地に染み込ませる行程がある。それはどの漆器でも一緒です。その後に、砥の粉と漆を混ぜたものを塗る下地の行程になる。その上に漆を塗り重ねて初めて漆器、という概念があるんです。でも、下地などの途中段階の質感って、強度さえあれば僕はすごくいいと思う。 -
この酒器は、
下地の行程で終わってる。
漆の人は絶対にしない。
-
「へぎ板」は、
人間ではなく、
木にとっての真っ直ぐ。
-
井上
工藤さんの作品の場合、耐久性に問題はないということですね。工藤
耐久性についての捉え方にもよりますが、木地が「へぎ」という技法で作られているからだと思う。たとえば一般的なロクロ成形、あるいはカンナで仕上げた木地の場合、下地だけだといずれスクラッチが入ってしまう。井上
それは木に無理をさせているから…?工藤
というよりも、導管に沿って割り裂いた状態が、木にとって一番自然な状態なんです。ノコギリで切断したり、カンナで削って平らにするということは、凸凹のある導管、つまり木の繊維を無理に切断してしまうことになり、断ち切られた導管からの水分の蒸発の差によって歪むので、狂いやすくもなる。そういう意味で、「へぎ」とはすごく自然な技法だと思うんです。人間にとってではなく、木にとっての真っ直ぐという意味で。普通は人間にとっての真っ直ぐを優先しちゃうでしょ? だから、歪んで狂って、木に仕返しされちゃう(笑)。その点、「へぎ」の場合は導管を断ち切らないから狂いが少ない。だから、塗装に頼る割合が少ないんです。
-
井上
以前、ご自分の作品をアートと工芸の中間に位置づけたいと、おっしゃったことがありましたね。工藤
一つの技を極めるという事が、苦手なのかもしれません。井上
それはどういう意味?工藤
伝統的な漆の世界でいえば、器物を塗り込めて蒔絵をするという技法が確立していて、日本の美術工芸の一翼を担っている訳です。
それらの高いレベルの技術力はすごいと思いますが、自分自身にとって大切な事は、ちょっと違う。
漆を何回塗っただとか、陶芸だったらこの色を出すのに苦労しただとか、技法自慢に陥りやすい判断基準が苦手。つまり、どれだけ大変な技法を駆使して作ったモノか、というスタンスではなく、出力された物自体の良し悪しを判断するスタンスでいたい。技法自慢ではない作品を僕は作っていきたいと思っています。 -
作りたいのは、
アートと工芸の中間に
位置する作品。
-
色々な技術を再構成し、
自分の中で熟成し、
出力するということ。
-
井上
それはすごくデリケートな問題で、ある意味では技法軽視とも受け取られかねない気もしますが?工藤
たとえば、本人が技法を重視したとしても、軽視したとしても、その結果は出力された作品に出てくると思うんです。井上
私は、技術は絶対に必要なものだと思います。だって、技術がなければ物は作れないワケだから。たとえばコンセプトが大切だと言っても、そのコンセプトを具体化するためには、技術が不可欠でしょう。ただ、技術だけあっても創造力がなければ、作家性のある作品は出来ない。工藤
技術っていうのはほとんど出尽くしていて、あとは再構成しか残っていないような気がするんです。井上
ああ、なるほどね。工藤
だから、一番小さな単位の技術をいろいろな所から吸収して、自分の中で再構成して熟成して出力する。それが、僕にとってアートと工芸の中間ということです。
-
井上
ご自分の作品の魅力はどこにあると思いますか?工藤
木の中から、一番いいフレームを取り出しているだけ。立体トリミングの作業ですね。自分で造形しているわけじゃないから。ずるいっていえば、ずるい(笑)。井上
でも、造形力があるからこそ、そのフォルムを引き出せると思います。見極める目がないとね。工藤
それはそうです。あと2㎜削るか削らないかを、どう判断するかですから。これはやってみないと解らない。だから、変な物も作りますよ、時には(笑)。 -


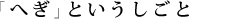


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net