
-
探せばきっと、
自分のやりたいこと
自分だけの道がみつかるはず。
-
井上
最近の陶芸界はどこか閉塞状況にあるように思えるんですが、田淵さんはどう思われますか?田淵
それは感じますね。飽和状態というか、どこへ行っても似たような器を見かけるというか…。もったいないなと思います。簡単には見つからないけど、探せばきっと自分のやりたいこと、自分だけの道があるはずと。井上
でも、それを求めていない人も多いんじゃないかな? 作家であろうとするよりも、生業というか、売れ筋のものをつくって、人気の店に置いてもらおうという職業的な志向を感じます。田淵
それもありますね。
-
井上
田淵さんは焼き物を選んでよかったと思いますか?田淵
はい、思ってますよ。自分が一生かけて突き詰めていきたいものを、見つけられたという思いがあるんで、それをもっともっとやっていきたい。それに、僕はこれから自分がやっていこうとしていることに対して、すごく興味があるんです。どういう表情が生まれてくるのか、どういうものが焼けてくるのかって。
そういう興味とか好奇心があったから、今までずっとやってこられたんだとも思います。同じように情熱を持っている人と話をすると楽しいし、そういうつくり手が増えるといいですね。井上
その興味や好奇心は、焼き物のどんなところに?田淵
焼き物ってどういうことか、土を焼くってどういうことかをよく考えるんですよ。窯焚きでも手間やコストの削減のため薪を購入したり、灯油と併用して焚いたりと、焚き方は人によってさまざまなんです。僕の場合、燃料となるその薪も、なるべく自分で段取りしたいと思っています。大変ですけど、チェンソーで木を切ったり、薪割りをしたりする作業も、自分にとってすごく大事なような気がしますね。
薪割りをしている時も体力がいるんですけど、割ったこの1本1本の薪が燃えてきれいな炎を出しながら、白い器にピンクや黄色や紫などいろんな景色を生み出してくれる。そう思うと、本当にワクワクしますね。井上
薪はどこから?田淵
近所のおっちゃんと「今度あれ切りに行くか」って。もちろん持ち主の了解を得てですけど、松くい虫にやられて枯れかけている木が増えていて、そういうのからなるべく切っていくので、逆に喜ばれたりします。井上
木の樹種は関係ない?田淵
やっぱり赤松がよく燃えるので赤松がいいですね。でも手に入る木もいろいろなので、状況に合わせて焚くようにしています。 -
これから自分がやっていこうと
していることに
僕はすごく興味がある。


-

-
井上
将来の目標は?田淵
白磁の可能性や薪窯の可能性をもっと広げたいし伝えたい。これは自分の使命だとも思っています。そこで生まれる美しいものを、一人でも多くの人に見てもらえるようなものをつくっていきたい。
海外でも今いろいろと発表の機会が増えているので、そこも視野に入れ展開していきたいと思っています。
また、陶芸界だけでなく、香川に縁の深い、イサムノグチ※8、猪熊弦一郎※9、中川幸夫※10、谷口吉生※11さんのような方々と比べられるような作家になりたいですね。井上
期待しています。どうも有り難うございました。
※8:イサムノグチ
1904-1988、日系アメリカ人の彫刻家、画家、インテリアデザイナー、造園家、舞台芸術家。1969年にパリのユネスコ庭園の仕事で、香川県産出の庵治石を使用。これを機に高松市牟礼町にアトリエを構え、日本での制作拠点とした。
※9:猪熊弦一郎(いのくまげんいちろう)
1902-1993、洋画家。高松市に生まれ、丸亀市に転居。丹下健三設計の香川県庁舎に壁画作品がある。丸亀市に「猪熊弦一郎現代美術館」。
※10:中川幸夫(なかがわゆきお)
1918年生まれ、丸亀市出身のいけばな芸術家。「前衛いけばな」の活動で知られる。
※11:谷口吉生(たにぐちよしお)
1937年東京生まれ。ニューヨーク近代美術館・新館設計を手がけた建築家。1991年に丸亀市「猪熊弦一郎現代美術館」、2004年に坂出市「東山魁夷せとうち美術館」を設計するなど、香川と縁がある。帝国劇場の設計で有名な谷口吉郎は父。
インタビューを終えて
田淵さんの器を初めて見た時、目の前のすっきりしたフォルムの磁器はとても好ましいもので、それが薪窯焼成で窯変した白磁と知って、かなりびっくりした。なぜならば、私の陶磁器学習の結果として『磁器は白きがゆえに尊し』『それを人類は求めて来た』という概念が頭の中にがっちり入り込んでいたから。
だから、田淵さんには『何故白磁を、匣鉢(さや)も使わず窯変させるのか』が聞きたくて、それが中心話題になった。そして彼からの答え『今の時代、ガス窯や電気窯もあり白く焼くことは、昔ほど難しいものではなくなっていると思う。そんな時代に生きる僕にとって、「より白く」という発想は全くないですね。』私の先入観は見事に吹き飛ばされ、小気味の良いインタビューになった。
井上典子
女性誌のリビングページ担当編集者としての活動の後、流通業界においてリビング分野の企画・プロデュースの仕事に携わる。2000年4月、作り手と使い手の間を介する(=仲立ちする)場として「ギャラリー介」を渋谷区東にオープン。ガラス、陶、木、金属、布など幅広いジャンルの作家の作品展を開催。2008年6月にギャラリークローズ。2010〜2011年までpanoramaのプロデュースを担当。
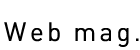
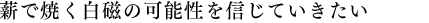

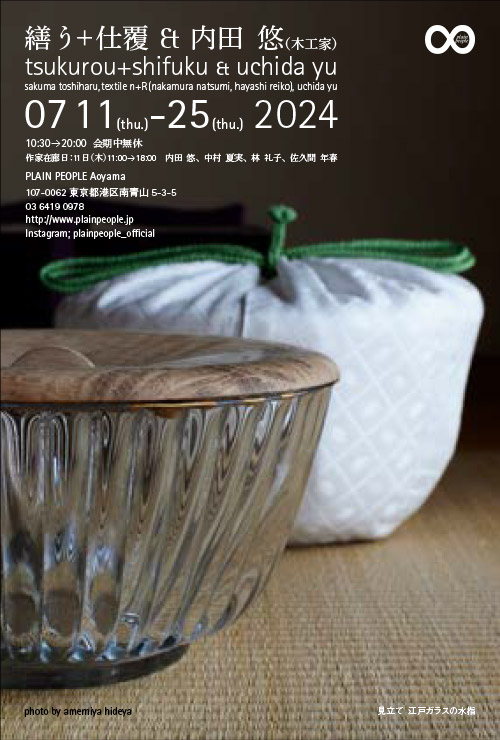
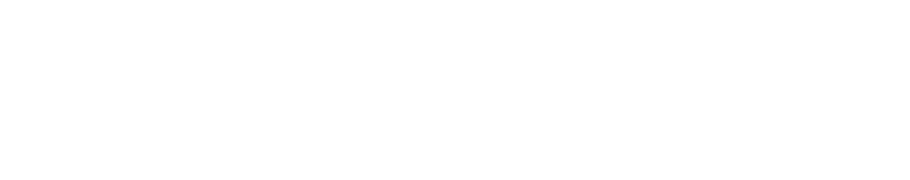 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net