Interview 桃居 広瀬一郎 Tohkyo / Ichiro HIROSE 聞き手:松本武明(うつわノート) / 文・構成:衣奈彩子 / 写真:大隅圭介 / Oct. 2014
80年代に感じた、時代に対する違和感
松本 gallery’s eyeのギャラリーの中では、桃居が、一番長く営業されていますね。
広瀬
オープンが、1987年ですからね。それまでは、まったく別の仕事をしていました。最初は出版社の編集の仕事に就いたんですが、長くは続かず、神田でコーヒー屋を始めました。いま考えると、きちんとした職業に就きたくなかったということだったと思うんです。あの頃は、4〜5年ごとに営業形態を変えていましたから。その後、30歳に近くなって、神田から青山に場所を移して、1982年に「K’s Bar」というのを始めました。出版、放送、広告代理店という、いろいろなメディアにいた友達たちが集まって話をしたり、面白いことをあれこれできるスペースを作ろうということで始めたんですけれども、これも明確にビジネスにしようということではなかったんです。
80年代って、やはりちょっと変な時代で、景気がよくて元気があって、自分もその時代を面白がってはいたけれども、一方で、高度消費社会に人々が流れ込んでいることに対する違和感が、いつも、もやもやとありました。国際社会でも日本の経済的な役割が大きくなってきて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」なんていう言葉が飛び交っていた。その中で、自分も、ビジネスでは成功していながら、何か、違和感を感じるというのがありましたね。
松本 その違和感が、その後の行動に影響を与えているんですか?
広瀬 おそらくそうですね。もともとは現代美術に興味があったんですが、そういうもやもやとした気持ちの中で、アートへの興味が薄れ、それまで私の視野に入っていなかったプリミティブな道具であったり、ロマネスクの建築であったり、縄文、弥生時代への興味が芽生えて、次第に日本の古い焼物を見るようになったんです。須恵器があって、鎌倉、室町があってと、歴史を見ていくと、あ、現代の焼物に繋がっているんだということに気がついて。現代の焼物を見てみると、自分を刺激してくれるものがあったんです。それで、お店や自宅のうつわを、少しづつまともなものにしていきました。
桃居の始まり
松本 なぜ、お店にしようと思ったんですか?
広瀬 自分の周りにいた、美術やファッション、建築に興味を持っている人たちが、食器については、きちんと選んでいないということに気がついたからですね。彼らのスイッチが一度入ったら、食器に対して、ヴィヴィッドな感覚を持つのではないだろうかと思ったんです。それで、まずは、自分が使いたいと思えるうつわを扱う店を始めようと、興味を持っていた作家さんにコンタクトをとることから始めました。
松本 そのころの食器の市場というのは、どういうものでしたか?

広瀬 当時は、食器を揃えようとすると、デパートの売り場で量産ものを買うか、美術画廊で有名作家のものを手に入れるかしかなかったと思います。これは、桐箱に入って五客セットというような高価なものですね。でも、自分が生活で使いたいものは、量産ものでも美術品でもなかった。その間に空白のゾーンがあるのが分かったので、需要はあるだろうと漠然と思っていました。
松本 80年代的なるものへの違和感、現代美術に自分の気持ちが動かなくなったことへの裏返しが、実感のある日常のうつわだったわけですね。
自分の時間をかける仕事として
広瀬 桃居を始めることによって、もしかしたらこれは、自分の時間をかけるだけの仕事になるのかなと。最初の3年間は赤字だったので、ビジネスとしての手応えはなかったですけど、いろいろなタイプの作家さんと話して、その能力や魅力を自分なりにエディットしていくこと、組み合わせてオーガナイズしていくことは、楽しい作業でした。コーヒー屋やバーの仕事とは、違った手応えを感じていましたね。
松本 広瀬さんがコーヒー屋を始めた70年代というのは、体制に属したくないというムードがまだ残っていた時代ですよね?
広瀬 残っていましたね。これはきっと、いまの人には、まったく分かってもらえないことだと思うんですけれども、僕も、まともに就職試験を受けて企業の論理の中で仕事をするというのは、違うんじゃないかと思っていました。一方で、政治的な運動というものにも、学生のころから違和感を感じていた世代ですね。社会運動は、最初から選択肢になかったけれども、かといって自分には何もできない、長いモラトリアムですね。
陶磁器への興味が自分を捉えるきっかけに
松本 僕は、そういう部分に、広瀬さんと作家の村上春樹さんとを重ねてしまうんです。村上さんもジャズ喫茶をされていましたけど、あの時代の、自分の居場所をうまく見つけられない人にとってのコーヒー屋とかバーという選択肢は、あったのかもしれないですね。
広瀬 そういう在り方自体が許されたというのは、ある意味、日本が経済的によかったからだと思うんですよね。あの時代、文化的な先端はずっと海外にあったわけですけど、そこに違和感を感じたときに、日本の文化史への振り返りが起こったんだと思います。80年代後半くらいから、日本人の海外に対するコンプレックスが、徐々になくなっていったと思うんです。僕の場合も、それまで日本的なものと自分がまったくシンクロしていなかったので、より新鮮な形で、日本の陶磁器や文芸の伝統をとらえることができました。

松本 モラトリアムから抜け出すきっかけになったんですね?
広瀬 そうですね。中学、高校、大学までは「自分とは何か」と内面を掘ることにしか興味がなくて、自家中毒だったと思うんですよ。でも、そういう病気って、行くとこまで行くと反転するもので、あるとき「掘っていっても自分なんてものはないんだ」ということに気がついて。自分がないとしたら、今度は「自分は何かによって作られている」と考えざるを得ない。両親からの遺伝子のレベルで支配されていると同時に、文化的な環境や状況によって自分が作られているのだろうと捉えたんですね。1948年生まれで、歴史の中で見れば、太平洋戦争の敗戦直後に生まれた世代。ということは、僕は、日本の近代後期の人間が抱えている病を、同じように抱えているはずで、そういう文化的な環境というものに、自分なりにどう決着をつけるのかというのが、自分の人生の後半のテーマだと思ったんです。
松本 そんなときに、うつわの作り手に出会ったと。
広瀬 はい。自分にはもうあまり興味がなくなったときに、いろいろな作り手それぞれが持つバイアスというか、ゆがみや、ゆがみ方の差異を見ていくというのが、ものすごく面白くなって。それが、いまの仕事のスタンスにつながっていますね。桃居は、絶対的にこういう焼物を支持するというのはないんですけれども、陶芸という広いフィールドの中にいるさまざまな作り手が、それぞれにある種のゆがみを抱えていると考えて、そのゆがみをいろいろなレンズを使いながら検証していくことの面白さを、常に感じながら仕事をしているんです。
日本人らしい制作物としての工芸
松本 工芸は、日本的なものですか?
広瀬 美術の中でも、とりわけ、私が興味を持った現代美術というのは、西洋由来のルールによって闘わせられているゲームなわけです。しかし、そもそも、日本人と西洋人の自我の成り立ちというのは文化的に違うはずなので、日本人が現代美術をやるというのは、どこか、アンナチュラルであるようなことのようにも思うわけですよ。アンナチュラルであるがゆえに、それを武器にして、そのルールの中で闘うというやり方は大いにあると思いますよ。村上隆さんをはじめとして、日本人で現代美術のフィールドで闘っているアーティストは、そういうのをテコにしてやっているところがあると思います。でも、もっと日本人が自然に取り組める、美的な制作物の有り様は何かと考えると、やっぱり工芸なんじゃないでしょうか。
松本 広瀬さんのそういう思想や哲学的な考え方をお聞きすると、扱う品物としては、アートのほうがしっくりくるんじゃないかと思ってしまうんですが、現代美術に持っていた興味が工芸にシフトしたと考えたらいいですか?
広瀬 そうですね。同時にそういう作り手が出始めたころなのかもしれない。川淵直樹さん、青木亮さん、花岡隆さん、村木雄児さん、僕と同世代か、ちょっと年齢が下の方ですね。少し経って、黒田泰蔵さんのような方も出てきて。彼らは、旧来の有名百貨店の美術画廊で作品を発表するのとは違うところで、仕事をしていました。

松本 青木さんも、もともとは現代美術をやっていて、焼物に転向した方ですよね。
広瀬 工芸というのは、基本的には、木、土、鉄などの自然素材と向き合って、その素材が持っている魅力を、作り手が受け取り想いをのせて差し出すもの。素材と作り手がキャッチボールをしながら、成立していくものだと思うんですけれども、素材が持っている力を自分のセンサーを使って感じ取るというのは、日本人が持つ独特の感性だなって思うんです。美術の作家で、彫刻家だったら、木も鉄も石も扱うし、画家だったら、絵の具という素材を使って表現しますけど、この場合の素材は、自分の表現のための手段であって、作家が素材を上から支配する構造になりますよね。工芸の場合、一元的に支配してものを作るというよりも、素材と対話しながら作っていくんだと思います。そこが工芸の魅力ですね。
松本 K’s barと桃居を平行して経営する時期は、どれくらい続いたんですか?

広瀬 10年くらいは続きました。50歳になって、昼夜の両方仕事するのが厳しくなったので、バーを閉めました。基本的にどちらもひとりでやってきたんですが、それが性にあっているようです。
松本 取扱い作家さんの数は増え続けていますね。
広瀬 オープン当初は、クラフトフェアもなかったですから、気になる展覧会を見に行ったり、あとは、作り手の方と縁ができると、その作り手が別の作り手との縁を呼び出してくれました。赤木明登さんとのお付き合いも、うちの展示を見に来てくれたことで始まったんです。まだ、下地の親方について修行中だったんですけど、独立したら、作品を見てくださいとおっしゃって。始めての展覧会を桃居でやってくれました。三谷龍二さんや安藤雅信さんを紹介してくれたのも、赤木さんだったと思います。
新しい作り手の時代を感じて
松本 桃居で取り扱うのは、いまでこそよく知られた作家さんばかりですが、当時は必ずしも有名ではなかったんですよね。
広瀬 はい。ただ「ああ、新しい作り手の時代がくるんだな」とは思っていました。赤木さん、三谷さん、安藤さんは、それぞれ、編集、演劇、彫刻と、工芸とは別のフィールドで仕事をしてきた。回り道をしながらこの世界に入って来た作り手というのは、作り手である以前に優れた使い手であったと思うんです。自分にとっての理想の暮らしというのがあって、その中で必要とされるうつわって何だろう、ということでものを作っていく。それが、いわゆる生活的な工芸というものの土壌を作ってきたという気がします。
松本 意識して、そういう作家を選んできたのですか。

広瀬 時代が召還する作り手というのがあると思うんです。そういう人を紹介したいと思っています。桃居を始めた当初は「〜〜焼」と産地で焼物が語られたり、朝日陶芸展や日本陶芸展、三越の伝統工芸展で選ばれて階段をのぼっていく作家が当たり前でした。と同時に、そういう個人作家の在り方自体が、賞味期限を迎えた時代でもあったと思うんです。暮らしの中で、気に入って使ってもらって、道具としてよりよく機能するうつわを作りたい。うつわは、それぞれの家庭に招き入れられてこそ役割を果たすものであって、それがうつわの醍醐味だという意識を持つ作り手が増えてきた。自分もそこに共感しました。
松本 広瀬さんが70年代に、時代に対する違和感を持ちながら、満足感を持てずに飲食店をやった結果、ギャラリーという仕事に辿りつき、こうして人生を選択してきたことと、赤木さんや三谷さんが回り道をして工芸に辿りついたことには、重なる部分があるような気がします。伝統的な工芸の家系に生まれて、技術を伝承していく作家との違いというか。
広瀬 手探りで自分が作るべきものを探し、作りたいという意思から道を選択するという形ですね。
桃居として、何を選ぶか
松本 桃居として、何を選んで何を選ばないのかというところが、気になるんですが。
広瀬 作品に何かを感じたら、あとはやはり、その人の人間としての佇まいとか、内側に持っているもの。技術的な完成度やスタイルというよりは、作品に内在している「どうしてもこういうものを作りたいんだ」という想いを見ているかもしれません。技術が高くてセンスがよくても、そういう「何か」が感じられないとあまり。例えば、新宮州三さんにお会いしたのは10年近く前で、当時の技術レベルはまだ十分ではなかったけれど、彼が作るものの中には、当時からその「何か」があったと思うんです。

松本 広瀬さんが紹介してきた生活的な工芸というのは、ここ20年くらい順風満帆だったと思います。作り手もお客様も育ってきた一方で、いま、飽和しつつあるかなという気もするんですが。
広瀬 これからは、生活的な工芸を引き継ぎつつ、その周縁をいく、若くて新しい作り手が育っていくと思いますよ。僕はいま、生活的な工芸が広く占拠したがゆえに、その周縁のマージナルな部分に追いやられてしまった工芸、そうしたところに新しい試みを始めている人たちがいるような気がしていて。そういう仕事に真剣に向き合って、紹介していきたいと思っているんです。
松本 具体的にはどういったものですか?
広瀬 普通の意味での用途とか役割とか道具性を持たないものですね。彼らは、用途とか目的を意識せずに素材と対話し始めている。これは旧来の美術とも違う、日本人的な感性や文化的遺伝子のみが作りうる固有の世界である気がしているんです。近代以降、僕らは、西欧的な美術の感性に支配されてきたので、工芸の中で“使えない工芸”がでてくると、すぐに排除しがちだし、そういうものは、美術のほうに分類したがります。でもよく考えてみれば、美術と工芸というのを分けて解釈すること自体、西洋的な解釈なわけですよね。新しい作り手は、美術か工芸かという意識すらなくて、もっと抽象的な意味で暮らしの役に立つもの、暮らしを気持ちよくしてくれるものを、ただ作っていると思うんです。そういうものを、生活的な工芸と親和させていく方向を探ってみたいと思っています。
工芸30年説
松本 広瀬さんが、最近ご発言されている「工芸30年説」でいうと、桃居がオープンした87年からまもなく30年。次なる時代への可能性を、アートと工芸が融合した生活の中のものに見ているんですね?
広瀬
はい。ただ、生活工芸の次にあるものが、それかというと違うかもしれません。すごく大きな存在になるとは思わないです。むしろ、いろいろなタイプの作り手がさまざまな挑戦をしていく時代になるんじゃないでしょうか。
もうひとつ、いままで自分が見てこなかったもので新鮮なものというと、日本の伝統工芸で継承されてきた細かい手仕事、超絶技巧のようなものです。ハレの世界で用いられて来たものなので、日常生活には関係ないと、こちらも生活工芸の周縁に追いやられているんですけれども、すごく日本的なものだと思うんですよ。暮らしの中にすぐ取り入れようということではなく、いつも目をむけて刺激をもらっていく。あるいは、いままでの使われ方とは違う楽しみ方を、僕ら自身が発見していく可能性だってあると思うんですね。これからは、そういうものと対話しながら、生活工芸の世界が豊かになっていくのがいい。むしろ、そういうものと積極的に対話していかない限り、生活的な工芸は、更新されないという気がしています。

松本 なぜ、そんな風に考えるようになったんですか?
広瀬
行動生物学の生みの親と言われる、エストニア生まれのドイツの生物学者・ユクスキュールの本を読んだんです。彼は「動物には、生物種の数だけ世界の見方があり、それぞれの“
お店が面白がっていないと、お客さんも面白がってはくれないと思うんです。お店の魅力って、どれだけどきどきしながらできるかっていうことですよね。店主が面白がっていることで、お客様が集まってくるという。
松本 広瀬さんの編集者的な視点が変わって来たということなんですね。
広瀬 そうですね。生活的な工芸を、もっと生き生きとさせるためには、外部の血と積極的に交わって、工芸の中に閉じこもっていては見えなかったものを見ていかないと、自分にも、生活工芸そのものにも、未来はないと思っています。

松本 広瀬さんは、時代に対する感度を持っています。桃居の取扱い作家を見ると、生活工芸の時代の断面図が見えてきますね。
広瀬 そういう人たちがデビューして、まだ手探りだった時代に出会えたというのは、恵まれていましたね。三谷さんにしても赤木さんにしても、作っているものは、もちろん魅力的なんですけれども、ちょっとお話するだけで、人間的な魅力まで感じられる。優れた作り手には、言葉ではなく発するものがあるように思います。
松本 展覧会をやるとお付き合いが長いですよね、10年とか20年。広瀬さんは、継続することに対して、高い意識を持っていると思うんですが。
広瀬 継続して付き合っていくのはいいですね。3年では見えなかったものが5年で見えたり、5年で見えなかったものが10年で見えたり。ものも、人も、そうですね。
これからの作り手、これからのギャラリー
松本 最近の工芸をとりまく状況やマーケットに関して、思うことはありますか?
広瀬 これまでは恵まれた時代だったと思います。バブル期の成長型経済が終わって、どうやって生活していくかということに意識が向いていた時代に、お店をやることができました。でもこれからは、すごく厳しい時代だと思います。桃居をこれまで経済的に支えてくれていたお客様というのは、ものを消費する楽しさが体に染み込んでいた人たち、スイッチが入れば、暮らしの内側を豊かにすることに消費がむく人たちでした。ところが、2000年代以降の新しい工芸の市場を支えるお客様というのは、日本がすでに成熟期に入ってからの消費者で、自分の身の丈にあった気に入ったものだけを買い、長く大切に使う人たちです。作り手も商い手も、そうした消費者と向き合っていかなくてはいけない。覚悟が必要です。いろいろな意味で、選択と淘汰という時代なのかなと。

松本 淘汰はありますか。たしかに裾野が広がり数が多いですよね。作り手も、ギャラリーやお店も。
広瀬 「これがやりたい」という作家のものでなければ、手にとらないというのと同じで、お店にも「これをやりたい」というものがないと。売れ筋を並べただけでは、成立しない時代になっていくんじゃないでしょうか。
松本 何を扱いたいか、こういう作り手を自分は紹介したいんだという、意思ですね。
広瀬 作る側と伝える側、そして使う側が向き合って、コミュニケーションしながらマーケットをつくっていく時代だと思います。
松本 そういう時代においてギャラリーの意味はあるんでしょうか。いまは、クラフトフェアなどで、作家が直接、販売することができますよね。
広瀬 出版界でも編集者はいらないんじゃないかと言われているようですが、僕は編集する人は絶対に必要だと思うんですよ。ギャラリストの目を通して、無数にある制作物のなかから、編集という選別を行わないと、消費者は、なんの手だてもないところで、ものを選んでいかなければならない。作り手の能力を選別して、キュレーションしていく人たちの必要性というのは、僕は、必要だと思いますね。誰でも作り手になれたり、発信できる時代が進めば進むほど、きちんとキュレーションできる人が必要なんです。ただし、その人に能力があるかどうか、その場がギャラリーとして機能しているかどうかは問われるでしょう。でも、優れた編集能力があれば、必要とされるものだと思います。生活工芸もギャラリーも、曲がり角にきているのは確かです。2020年あたりがめどになって、作り手の再編、店の再編、消費者の意識の再編が進むんじゃないかなと思っています。でも悲観はしていませんよ。不思議なもので、新しいものが必要になる時というのは、自然とそういう能力を持っている人が準備されているものなんです。だから、もうその芽はでているような気がします。
松本 いろいろな人が時代をまとめ始めて、その中で、次の時代も見えてくるということですね。

広瀬 gallery’s eyeでは、さきほど話したような、いままで桃居で扱ってこなかった人を紹介しようと思っています。鉄のオブジェの渡辺遼くん、泥彩木工の林友子さん、人間国宝の室瀬和美先生に師事していた、蒔絵の樋渡賢さんなどの作品です。
松本 とても楽しみにしています。今日はありがとうございました。

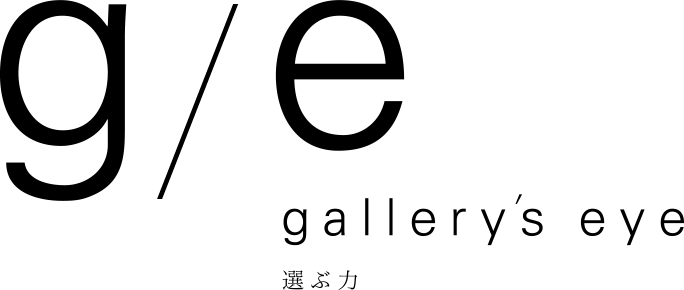











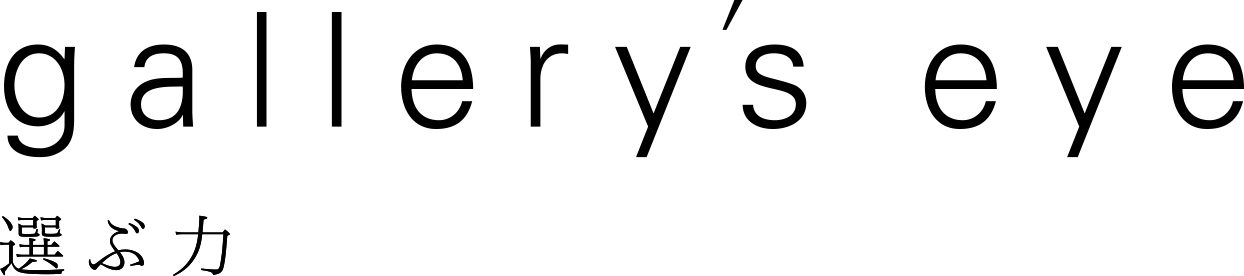


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net