Interview さる山 猿山修 saruyama / Osamu SARUYAMA 聞き手:松本武明(うつわノート) / 文・構成:衣奈彩子 / 写真:大隅圭介 / Oct. 2014
余白のあるデザインへの意識
松本 猿山さんは、社会人としての最初の仕事が、デザインをすることだったんですよね。
猿山 アパレルのメーカーにいましたね。その後は、広告代理店で制作の仕事をして、グラフィックデザインの流れをひととおり身につけました。
松本 学生時代は、舞台をやっていたと聞きましたが。
猿山 高校くらいから、バンド活動や舞台美術をやっていました。演劇はいまも続けていて、舞台用の音楽を担当しています。
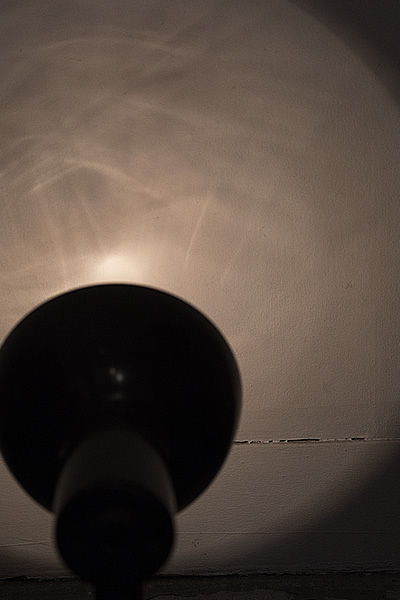
松本 大学は、美大に入ったわけではないんですよね。
猿山 美大にはあまり興味がなくて、大学の法学部に入りましたが授業を受けたのは数日ですね。何をやっても違うという気持ちがあって、学生時代は、とにかくだらだらしていました。仕事を始めても同じで、こんなはずじゃない、こんなことしている場合じゃないと、いつも思っていましたね。
松本 でも、なにかを表現したいという思いはあったんですよね。バンドとか舞台芸術とか。
猿山 視覚的効果のあるものや、それを作り出すことに興味があったんだと思います。
松本 その頃から、余白のあるデザインを意識していたんでしょうか。
猿山 あったと思います。好みはあまり変わっていないですね。出演者のいない芝居、ダンサーも俳優も使わずに40分の舞台を見せるというのをやったこともありますから。舞台にスライドを投影して、爆音をミキサーで演奏して、その後いきなり暗転。上から畳一枚分の板が落ちるという演出をしたこともあって、そういうのが、自分にとっては、余白のひとつでした。それから、オーブリー・ビアズリーの白と黒の世界が好きでしたね。絵の部分と余白の部分が共存するビアズリーのエログロの世界に魅かれると同時に、自分だったらそれをどう表現するかと考えたこともありました。自分だったら、あえて見るに絶えない描写を排除することで、そこにエロスを想像させようと考えたり。想像すること自体が余白のひとつだと捉えていました。音楽も、静かなものというよりも、ずっと続いているノイズとかヘビメタの爆音が好きでしたね。ノイズや爆音が続くことは、不快なことだけれど、そこにどっぷり浸かることで何もない様な感覚、つまり余白に陥ることがあるんです。

猿山美学のルーツをひもとく
松本 猿山さんのデザインを見ていると、具象的な対象を抽象化していくような感覚がある。理屈ではなく、対象とするものに生命そのものが反応してしまうような、生理的な感覚が強いのではないかと感じます。なんというか、それは、食に対する嗜好にも通ずるような生理的な感覚のように思えるのですが、どうですか?
猿山 それはあるかも知れません。子供の頃、給食の時間にみんなが好きだと言うものは、どれも僕が嫌いなものだったんです。物心ついた頃から、野菜以外はあまり食べられない子供でした。カレーライスやハンバーグじゃなくて、春雨サラダや卵料理というみんなが食べたがらないものが好きでしたね。給食の時間に山ほど余っているものが、僕の好きなものだということに直面した時に、子供心に、自分にはどう頑張っても人と共感できないものがあるんだなって思ったんですよ。体が受け付けない生理的なものがある。
松本 みんなが美味しいと思うものを、自分は美味しいと思えないというのは、苦しいですね。人と共有するということに信頼を持てないわけでしょ。美味しいとか、良いとかいう生理的な感覚が、人と分かち合えず、受け入れてもらえないというのでは、世の中で良いとされていることに対して常に懐疑的になりますよね。
猿山 はい。色に対しても興味がなかったですね。作ることは好きで、図工の時間は大好きでしたけど「さあ、色を塗りましょう」となると欲しい色がないんですよ。白か黒がいいなと。
松本 子供は、大抵、ヴィヴィッドな色が好きなのにね。
猿山 色は塗らなくていいのにといつも思っていてデッサンが大好きでした。写生大会も広い風景ではなくて、葉っぱ一枚とか、近くにあるものを細部まで書き込み、背景はあえて描かないのがかっこいいと思ったり、教科書にある素描を見てここだけ色をつければいいのにと思ったり、そういうことばかりして美術の先生に怒られていました。大人の顔色をうかがったり、友達のやることに一生懸命合わせている子供時代でしたよ。

松本 肯定してくれる人はいましたか?
猿山 いないですね。
松本 そうなると、自分の価値観を自分で確立していくしかないですよね。食への意識や違和感は、グラフィックなど視覚的な興味にも通じているんですか?
猿山 そうだと思いますね。例えば、血というのは赤いですよね。赤色の絵の具を使うのは、何ともないんですけど、赤色の血が、自分の体や動物など生きているものから出てくることには、体が硬直するほどの恐怖を感じるんです。肉は、動物の匂いを感じて食べられません。エログロの世界観が好きという感覚はあるけれども、それは現実ではなくて、あくまでも絵の中にある世界への興味なんです。グラフィックの世界に進んだのも、自分にはたどり着けず、受け入れられないエログロな生命への憧れの裏返しだったと思うんですよね。
松本 それは、独特な感覚ですね。
古道具さる山とデザイン
松本 ところで、独立したのはいつですか?
猿山 23歳で独立して、デザイン事務所「ギュメ」を始めました。「ギュメ」というのはフランス語の引用符なんですけど、引用=真似ではなく自分がいいと思うこと、人に語って恥ずかしくないことをやっていこうという意味で付けました。西荻窪に、グラフィックなど自分の作品をディスプレイしながら仕事もできるお店兼事務所を持ったのが、26歳です。グラフィックの他に、店舗デザインもやるようになり古い家具をメンテナンスして取り入れるうちに、お店でも扱うようになりました。市場で人が目もくれない古道具を買い付けては直し、アンティークの白い焼物とグラフィックデザインの仕事と一緒にディスプレイしていましたが、僕の仕事の内容を見るよりも、古道具を欲しがる人の方が多くなって、半年もたたないうちに古道具屋をやることにしました。

松本 それが「古道具さる山」ですね。
猿山 デザインソースであつめていた古い食器がものすごい量になっていたので、主にそれを並べました。18~19世紀くらいのフランス、イギリスのものが中心で東南アジアで買い付けることもありました。インドネシアでは、田舎に行くとオランダの19世紀の焼物があったり、フィリピンにも中国の古いものがありましたよ。
松本 当時、麻布十番にあった「うちだ」や目白の「古道具坂田」の影響は受けていましたか?
猿山 いいえ、当時は、内田さんも坂田さんも知らなかったですね。でも、お客さんに「坂田の弟子なのか」と聞かれる事がよくありました。そんな中、ある日、坂田さんがいらして箪笥や道具を買ってくださって、納品するときに初めてお店にうかがいました。相当ショックを受けましたよ。お店としてなんてかっこいいんだろうと。僕が知っている店の中で一番かっこいいと思いました。それからは、余計な意地というか、できるだけ影響を受けないように頑張りましたけどね。
松本 いまでこそ、西洋骨董を扱うお店は多いですが、そのころは西洋骨董といったら、エミール・ガレやデコラティブなアンティーク家具ですよね。猿山さんは、そういう時代にいわゆるブロカントを紹介し、生活に取り入れることを他に先駆けて提案したんですね。「古道具さる山」として知名度があがり、人気も確立していたのに、なぜ麻布十番へ移転したんですか?
猿山 西荻窪時代は、休みになるとまだお店を始める前の「タミゼ」の昌太郎(吉田昌太郎さん)や「さかむら」の坂村たちがずっと店に入り浸っていましたが、僕自身は、麻布十番の「うちだ」の内田明夫さんのところによく通うようになっていて、近くに来ないかと誘われたんです。古道具をやるお店が他にも増えてきたし、デザインの仕事も増えて来たので、今度こそ、自分の仕事を見せる空間を作りたくなりました。自分しか興味がないと思っていた領域に、他の人が食いついちゃうと、一緒に盛り上がるというより急に興味がなくなっちゃうというのもあって、「さる山」の新しい形を求めて西荻窪から麻布に移転したんです

松本 先駆けてやってきたことを、死守しようとは思わなかったんですか。
猿山 なかったですね。僕がこだわっているのは、西洋骨董が持つニュアンスや形、時代背景であって、古いものへの純粋な愛というのとは違うんです。コレクションすることに興味はなかったので、あまり執着はしませんでした。
作家をプロデュースしてものを作る
松本 デザインをして作家さんと一緒にプロダクトを作り始めるのもこの頃ですか?
猿山 それは、10年くらい前からですね。井山三希子さんとの出会いがきっかけです。井山さんが作っていた苔玉用の小さい鉢がすごく良くて。面取りした面の部分を丁寧に指でならして仕上げたものだったんですけど、もともと面を意識したうつわに興味があって「一緒に食器を作らない?」と誘ったんです。うちで井山さんの展示を企画する度に、古いものを見せてアドバイスをしているうちに、井山さんの方から「具体的にディレクションしてください」と言われました。
松本 その後は、岡田直人さん、竹俣勇壱さん、寒川義雄さん、辻野剛さん、濱中史朗さんをプロデュースして、作家さんとの関わりも広がっていきましたね。また流通側の「東屋」さんと共同でプロダクトの開発をしています。東屋さんとのプロダクトは、もうどれくらいありますか?

猿山 「東屋」で取り扱っているものだけでも、サイズ違いを含めて300種類はありますね。
松本 相当な数ですね。流通側と一緒になって作家をプロデュースすることの面白さは、どこにありますか?
猿山 デザインもそうですけど、主役がいて、その主役に対してなんらかの関わりを持つということですね。職人あがりの人か、ずっと個人でやってきた作家か、それまでにどれくらい経験があるかなど、人によってアプローチの仕方を変えていく必要があるところが面白いです。職人として10年以上やっていたという人は、圧倒的に技術があるので、こちらの要望を的確に理解してくれるんですけど、一方で、ずっと作家としてやってきた人というのは、要望に対して予想できなかった到達点を返して来たりするので、これもまた面白い。それぞれの良いところや特徴を考慮しながら進めていくという作業は、手応えがあってやりがいがありますね。自分にとっても身になる経験です。作家は、いまはこうでも、一年後には絶対にもっと良くなっているんですよね。その分、いまはお披露目と考えて一年後にもっといいものを流通させていこうという様に、個別に話をしながら進めることもできます。商品が完成して、流通が軌道に乗るまでには1年以上かかることが多いので、そういうスパンで進めても上手く行くんです。でも流通の仕方や利益まで見据えて企画する体制ができたのは、ここ数年のことですよ。たくさん売れなければ成り立たない仕事なので、もう少し体制を整えたいと思っています。

ギャラリストか否か
松本 デザインの仕事とギャラリー運営は、いまどういう割合でやっていますか?
猿山 ここ数年は、プロダクトの開発が半分近く。その他がグラフィックデザインとギャラリー運営です。
松本 つまり、当初、西荻窪で目指していた事務所兼ギャラリーのスタイルになってきたんですね。
猿山 自分では、ギャラリーという言葉を使ったことはないんですよね。西荻窪時代は「古道具さる山」、元麻布は「さる山」。自分の個人的なスペースとして、ここでは、できるだけ自分がやりたいことを表現したいと思っています。作家のものを展示する場所になることもあれば、古道具を売る場所であろうとすることもあり、ものを売らないこともある。大きなプロジェクトが進行している時には、ドアさえ開けないこともあるんです。そうなると、ここはどういうスペースなんでしょうね。
松本 ギャラリストという意識は、ありますか?
猿山 ものを紹介していく側という意識はありますね。それは、自分がすごく大事にしていることでもあります。
松本 猿山さんは一度も共同イベントに参加したことがないそうですが、今回gallery’s eyeに出展するのは“選ぶ力”という主旨に共感したということでしょうか。
猿山 松本さんの話が、面白かったんですよね。クラフトフェアのことについても、自分の中で腑に落ちないところはあったんですが、具体的に言葉にしようという考えは、僕にはなかったんです。リアリティのないことだったんだけど、松本さんのおかげで、僕も同じ様なことを考えた事があったなと思い出して、急にリアリティを感じてしまった。こうして、改めて考える機会をもらうのは、面白そうだなと思ったんです。
松本 猿山さんは、編集者であり、作り手であり、そしてやはり、きちんと選んでいる人ですよね。自分の世界観が確立していて、選ぶ眼、選ぶ力を持っている人であると同時に、多くのことを先駆けてやってきた。だけど、自分ではそのことを特に主張はしない。僕は、それはもったいないことだと思います。猿山さんは、古いもの、作家もの、デザイン、空間などすべてに対して眼があるギャラリストだと思うんです。



濱中史朗さんとの仕事
猿山 紹介する側にはきちんと選ぶ責任があって、それがギャラリストの仕事であるとするならば、僕にとっては、濱中史朗とやっていることが、一番ギャラリストらしいことだと思います。彼がいまやっていることを、どういう形で伝えるのがいいかを考え、その上で、どういうことをやってほしいかを伝え、年に一度、個展をする。次はどうしたいか、どうして行くのがいいか、いまの仕事をどう今後に繋げるかを一緒に考える。これは、ギャラリストの仕事と言えますね。それ以外は、プロデューサーかデザイナーという意識の方が強いです。
松本 濱中さんに惚れ込んでいる理由は?
猿山 まず、作り手として無条件に憧れたんですよね。それで声を掛けたんですけど、一緒にやり始めてからは、自分がこうだろうと思ったことが相手にとってもそうだったというのを、お互いにずっと繰り返していますね。僕がこうしたいと思っていることが、何も言わなくても、彼の方から匂ってくるんです。明確な意思表示をしなくても、思っていた方向に向かうんですよね。そして、ある段階で必ず小気味よく裏切られる。荷物を開けるときに、必ず、ああこう来たか、こんなことを企んでたのかとなるんです。いい意味でやられちゃうんですよね。あんなに楽しい開封作業はないですよ。もう10回近く一緒にやっていますけど、毎回そうなんです。毎年見事に楽しませてもらっています。

2014.12.13~21 濱中史朗展 "alternative white" フライヤー 写真/渞忠之
松本 最近の工芸やアートについて、感じることはありますか?
猿山 これから、さらに新しいクラフトフェアも生まれるでしょうけど、自分では、あまり足を運ばないのでよく分からないんです。生活工芸ということに関して言えば、赤木明登さんの登場はショックでした。赤木さんの漆器は、誰もが好きなんじゃないかなと思いましたね。赤木さんは、作り手である前に、使い手や紹介者としての自分がいて、その視点で欲しいものは何かを考え作り始めた人です。そういう人が漆の世界には、それまでいなかったわけで、それが焼物の世界だと誰になるのか、自分なら誰に声を掛けてどういうことができるのか考えるきっかけになりましたね。当時、僕も漆の組碗を作りたいと思っていたんですけど、図面をひいて産地に行って職人さんを訪ねてもうまく行かなかった事が、赤木さんにお願いしたらあっけなく出来上がった。結局、赤木さんか、とちょっと悔しかったですけどね。

松本 それもまた、作家と組んで作る面白さですね。今日は、ありがとうございました。

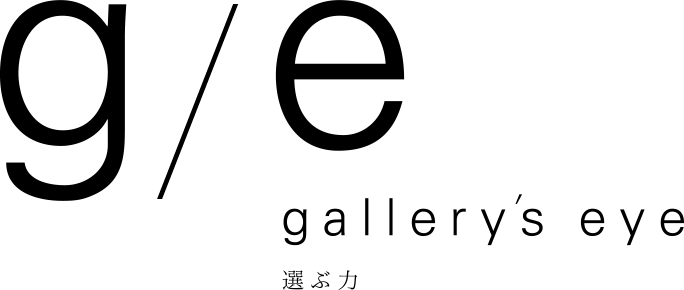











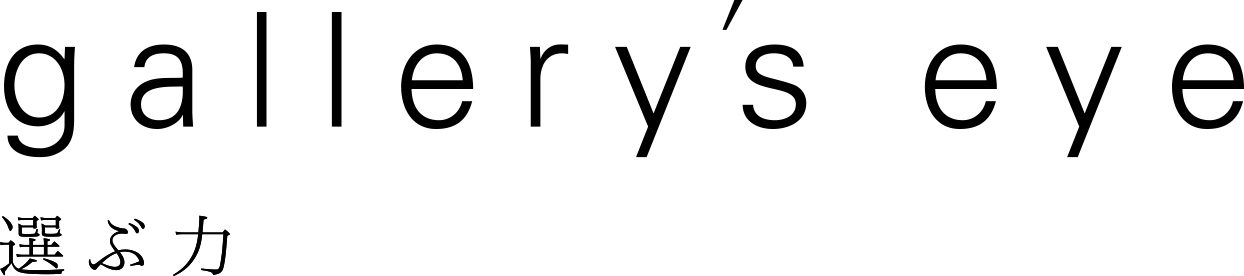


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net