Interview feel art zero 正木なお feel art zero / Nao MASAKI 聞き手:松本武明(うつわノート) / 文・構成:衣奈彩子 / 写真:大隅圭介 / Nov. 2014
ゼロの状態で作品と対峙すること
松本 正木さんは、どういう経緯でギャラリーを始めたんですか?
正木
私は、短大を卒業後、広告やファッションなどいろいろな仕事を経験しました。というのも、環境や人権問題といった社会的なことに興味があって、ボランティア活動などを優先していたので、その都度、時間の融通がきく仕事を選んでいたんです。
そんな中、ある時、吸い込まれるように名古屋市内の現代アートギャラリーに入ったのが、ギャラリーというものとの出合いでした。そのギャラリーでは、何もない空間にオブジェのようなものが、ぽつんぽつんと展示されていて、アーティストの名前も説明もなく、正直、どこがいいのかさっぱり分かりませんでした。もちろんギャラリーの方は、その作品をいいと思っていて「これ、すごくいいでしょう?」と声をかけてくる。
「何なの?この世界は」と思いつつ、私はこの時初めて、何にも頼らずに自分の眼だけで見なければ分からない世界があることを知ったんですね。心のどこかで、このよく分からない世界の存在を面白いと思うと同時に、直感的にこう感じました。「私は、いつかこういう場所にいるだろうな」って。実際に、いまギャラリーをやっているんですから不思議ですね。
松本 ボランティアをしていたということですが、人に何かを与えるとか、提供するということへの意識はもともと強かったんですか?
正木 祖父が、明治生まれの書道家で、近代日本のゆく末について熱く議論を交わした世代でした。面倒見がよく、家を抵当に入れてまで困っている人の世話をしたため、貧しい人から学生、市長までいろいろな人に慕われていたそうです。そうして世話をした人が、時を経て立派な身分となりお礼を言いに来てくれることもあって、決して裕福ではないけれど、精神的に豊かな家族だったという話を、私は母からよく聞いていたんです。その祖父の兄弟に蒔絵の人間国宝の高野松山がいて、美術館などで作品を見ていました。身近に工芸の話題があったので、子供心に、作る人と使う人、それを繋ぐ人がいるという豊かな文化にも憧れていたんだと思います。小さい頃に「私、パトロンになりたい」って母に言った事があるみたいなんですよ。

松本 ギャラリーというのは、それに近いものかも知れないですね。
正木 確かに自分の眼で見て、作品や作家に賛同するということは、パトロンになるということに近いかも知れません。人に教わって見るのではなく自分の感性で見る世界。それによって感性はもっと磨かれていくし、その人自身も変化していくと考えると、自分の眼で見る事は、生きることと直結している行為なんですよね。ギャラリーというのは、生きるための感性を刺激する場所なのかも知れません。
日々の些細なことにさえ感動する力
松本 感性を刺激するようなギャラリーをやろうと思い始めたのは、いつ頃ですか?
正木 具体的には、28歳の頃。2003年ですね。その頃、多治見の「ギャルリ百草」に行く機会がありました。和の空間を使って、生活のものをアートのように展示しモダンに見せるというお店は、当時あまりなかったんです。身の回りの生活のものさえも、自分の眼で見て、感じて、選んで変えていかなければ、世の中は変わらないと思う気持ちに拍車がかかりました。
松本 それまでは、ボランティアや社会運動を通して体制や権力など大きなものに立ち向かい、変えていこうとしていたわけですよね。
正木 そうですね。でもよく考えてみると、私は、活動家だったわけではなく、一般市民として世の中を変えていきたかったんです。私は普段から「感動する=感じて動く」という言葉を大事にしているんですけれど、人間というのは日々の些細なことにさえ感動する力を持っていて、その感動によって得た力が、いずれ社会を変えることもあるかも知れない。「ギャルリ百草」に通っていた頃、そういう理想がより具体的に見えて来た時期でした。
松本 具体的にお店を開いたのはいつですか?
正木 30歳の頃、2004年に、名古屋の雲雀ヶ岡で「生活装飾life deco」というセレクトショップを始めました。日本の骨董、ヨーロッパのアンティーク、旅先で見つけたもの、安藤雅信さんなど作家もののうつわ……、小さな博物館みたいな感じが好きだったので、古いガラスの破片や瓶なども取り扱っていました。私にとっては、それも生活を豊かにするものだったんです。ガラスの破片を美しいと思って買う人は、アートのセンスがあるに違いないと思っていて、そういうお客様を開拓したいというのもありました。実際に、そういうお客様はたくさんいて、翌年の10月には、ショップの上階に、feel art zeroというギャラリーを始めました。この名前には、何もないゼロの状態でものと対峙するという意味が込められています。店名の後に、数字のゼロに横線を入れたマークをつけました。これは、宇宙のイメージでもあって、自己の中の宇宙を探究するきっかけになるようなスペースにしたいという思いを込めたんです。2007年には、ビルの立て壊しに伴い、名古屋の中心地にもう少し近づいたこの場所に移転しました。

自分の感性の振り幅を検証する
松本 現在の場所での最初の展示は、誰でしたか?
正木 内田鋼一さんです。工芸も現代アートもカテゴライズせず、ノンジャンルでやりたかったので、内田さんにお願いしました。大きな鉢をたくさん並べた展覧会で、底辺の造形が美しい鉢だったので、それを目の高さで見られるように展示するなど趣向を凝らした面白い展覧会になりました。
松本 展覧会を企画するというのは、正木さんにとってどういう意味がありますか?
正木 展覧会を企画するということは、自分が受け入れられるものの振り幅を見ていく作業でもあります。だから、自分の眼で選び、使って経験したものでないと紹介できないですね。自分も含めて20〜40代というのは、いいものを見たり経験することで、物事により興味が出て価値観が変化したり、選択眼に幅が出る可能性を秘めた時期だと思うんです。10年後、20年後ではなくて、いま経験すべきことを私自身も経験して、自分の感性にはどれだけの振り幅があるのかを感じながら、いいと思うものを伝えていきたいと思っています。
松本 自分でも、いろいろと所有するんですか?
正木 なんでも手に入れるということはないですが、身銭を切って体験するということは大事にしていますね。私にとって所有とは、ものと自分の間でエネルギーの交換をすることなんです。もののエネルギーを受け止められるかどうか、自分に問いかけるということですね。「私は、これを本当にいいと思っているの?」「どうなの?」「本気で思っているなら、買ってみなさいよ!」と自分にあえて負荷をかけて買えるかどうかを試すことがあります。それが、数万円のものの時もあれば、数十万円、それ以上の時もありますが、単にものが欲しいというのとはちょっと違って、買うという行為を通して、自分が許容できることの振れ幅を見ているんだと思います。

松本 正木さんは、売るという事にも強い意志を持っていますね。
正木 一番大切にしているのは、感じてもらうことですが、お客様が自分でもどうにもできないくらい感じ入り、突き動かされて、作品を買ってくれることはとても嬉しいことです。「正木さんのところに来たら思わず買っちゃったじゃない、どうしてくれるのよ」と言われるくらい力を持つ作品を扱いたいと思っています。アーティストには、それだけのものを要求するし、自分自身も、そこまでの作品や作家を見抜き、ここに引っ張って来る力が欲しいですね。
松本 お客様には、どんな風に作品を勧めるんですか?
正木 基本的には作品を前にして「これどう? いいでしょ」というストレートな接客ですよ。長くお付き合いをしているお客様は、好みが分かるので、それぞれにご案内をして勧めることもあります。ものと人をマッチングさせるというのも、私の役目だと思っているので、自分がいいと思うものをこの人なら分かってくれるだろうと思うと、相手をその世界に引き込んでしまいますね。それまで知らなかった初めてのものに手を染めてしまう、あのなんとも言えない興奮する感覚を、共犯者のようにお客様と一緒に味わっています。ギャラリーでは、作品に突き動かされて人生が変わってしまうような経験だってできると思うんです。経験した人にしか分からないことかも知れないですけどね。

ギャラリーでは、究極の選択をすることもできる
正木 ギャラリーをやっていると、ものを買うことをきっかけに、人が究極の選択をする場に立ち会います。ギャラリーというのは、誰もが飛び込める世界ではないし、飛び込むことが必ずしもいいことではないとも言えると思います。ここにあるものと向き合う強さと、その経験を自分のものにし乗り越えるだけの資質が必要な世界でもある。そういう意味では、ものに出合うというのは、楽しいことばかりではないかも知れません。でもそれを乗り越えたら、新しくて面白い世界が広がっている。その瞬間に立ち会えることが、ギャラリストをやる醍醐味です。
松本 作品を見てもらうために、どんなことを心がけていますか?
正木 一年間にやる展覧会をバランスよく編成することは、とても重要ですね。アーティストに無理をさせるとそれが作品に出てしまうので、相手の意気込みや制作状況を見ながら、いいコンディションで準備をしてもらえるように配慮します。ギャラリーと作家の意気込みを伝えるグラフィックデザインやDMも大事な要素です。DMの写真は、最初から、写真家の辻徹さんにお願いしています。辻さんの写真が、広く人に伝えてくれたことは大きいと思いますね。あとは日々の積み重ね。いらしたお客様にいいギャラリーだと思っていただけなければ、リピートして来てもらうのは難しいですから。
松本 正木さんは、感性が鋭い人なので、もっと感覚的に企画をしているのかと思っていました。きちんと編成をして人に伝え、作品を持ち帰ってもらうために、日々努力をしているんですね。
正木 ギャラリーをやるよりも、もしかしたら自分で作品を買うほうが、金銭的には、作家を応援できますよね。それでも、ギャラリーとして多くの人に紹介したいと思うなら、その意味を理解してきちんと伝えなくてはいけないと思います。新しい作家さんとの出会いも、そうですね。基本的には、予感や直感を大事にしていますが、自分がただ好きというだけで選ぶわけではないんです。好きなだけなら自分が買えばいい話ですから。feel art zeroにこういう要素があってもいいなとか、お客様にそろそろこういう経験をしてもらいたいなという視点でも選んでいます。
松本 feel art zeroのユニークな切り口や熱い思いは、DMやグラフィックからよく伝わって来て、見に行きたいと心動かされますよ。いま見せたいものは、どんなものですか?
正木 日本の現代アートというのが、いま、変わって来ていると思うんです。日本人は、明治以降、西洋の美術観に支配され影響されて来たといわれるけれども、日本人が本来持っている美意識というのがあって、現代の作家さんの作品には、そういう日本人としてのDNAが自然と出てしまっているんじゃないでしょうか。例えば、植松永次さんの作品は、日本的でありながら普遍性があって世界に通用するもの。いままでは、工芸と言われてきたものかもしれませんが、そういうものの中に工芸の枠にはおさまらないものがある。そこに、日本のアートの未来や方向性が秘められていると思います。これは、アートVS工芸とジャンルを区切っていたら気付かないことだったのではないでしょうか。ノンジャンルで見せていく必要性を強く感じています。

松本 正木さんは、地球暦の展示や食のイベントなど、もの以外のジャンルにも挑戦していますね。
正木 人は、経験することでしか成長できないから、買うことだけに限らず、いろいろな経験を提供したいと思っています。地球暦では、太陽系の大きさを一兆分の一に縮小したインスタレーションの中で太陽系の研究の展示や講演会をしています。講演会は、1週間に5〜6回やるんですが、毎回大盛況なんですよ。これをきっかけに初めてうちのギャラリーに来たという人が多いのも嬉しいことです。初めての人、知らない人がまだまだいるというということは、忘れずにいたいことのひとつです。
ギャラリーだからできる経験というものを残したい
正木 地球暦は、100年後の地球について考えてもらうためのお手伝いという感覚でやっています。ギャラリーには、普遍的なことに取り組む役目があるんじゃないかと。そうすれば、たとえこのギャラリーがなくなっても、ここで得た経験は、人々の中に残っていきますよね。究極を言えば、それが理想です。
松本 アートを、美術館にある手の届かないものとしてではなく、自分たちの生活と繋がっているものと捉える人は、いま、増えているのではないでしょうか?
正木 アートや工芸を手に取る場所や作る人が増えているのは、感じますね。日本人には、季節感を楽しむ文化的素養や民族性がありますが、そうして毎日の小さな変化を表現することが暮らしを楽しむことに繋がっていると思うんです。feel art zeroも、衣食住を楽しむのと同じようにアートに触れられる場所でありたいと思います。
松本 経済的にゆとりがある時代ではないですが、身の丈にあった本物を見ている人は多いかもしれませんね。
正木 身の丈にあったものもいいけど、身の丈というのは、日々伸びていくもの。自分の価値観を決めつけて、アクシデントを恐れるのもつまらないと思います。ギャラリーは、ふらりと訪れる場所でありながら、いい意味で、人にアクシデントを起こす場所でありたいです。
松本 アクシデントというのは、具体的にはどういうことですか?
正木 例えば、植松永次さんの作品は、うつわであってうつわではないところがある。作家が持っている人間の本質みたいなものが表現されているから、アートや工芸に詳しくない一般の人にも響くんだと思うんです。見ているだけで、ごく自然にアートと工芸の境目を越えることができる。これもひとつのアクシデントですよね。こういう作家さんは、お客様の裾野を広げてくれると思います。内田鋼一さんもそういう作家です。絵画にも、いままで絵を買わなかった人が自然と買ってしまう作品というのがありますよ。



2014.11.15-11.30 / 植松英次「土から」会場風景
松本 アートフェアに参加したり、パルコの展示をディレクションしたり、正木さんは、ギャラリーを離れた他のところでキュレーションをすることにも興味があるんですよね。
正木 そういうパブリックな場所では、美術、工芸、自然科学、テクノロジーも含めた表現ができるんじゃないかなと思うんです。広いスペースなら、ストーリーに沿って作品を紹介することもできます。こことは違うことが表現できると思うので、いろいろとやってみたいですね。
松本 クラフトフェアなど、お店を仲介せずに、作家が直接売るということが広がっている昨今、ギャラリーが企画をすることの意味は、何でしょうか。
正木 クラフトフェアも含め、作品に触れる場所に選択肢があるのは、いい事だと思います。作家さんから直接聞くからこそ伝わる事もあると思うんです。一方で、ギャラリーでしか見えないものも確実にある。ギャラリーの真っ白い空間でゼロの状態で見ることで、作家が内面に抱えている厳しさや作品に込めた魂など、作家自身が隠していても見えてしまうものがあるんです。それは、自宅に持ち帰って見えるものともまた違う。ギャラリーというピリっとした緊張感のある空間で、距離を保って作品を見るからこそ見えるものがあると思います。私は、いつも、アーティストを舞台にあげるつもりで展示をしています。もっと言えば、お祀りしている感覚です。祀るとは、場の力を上げること。ものづくりというのは、ある種、神秘的な行為で、その場の力をあげるパワーを持っているんですよね。そういう意味でも、ギャラリーで買うという事は、お客様にとっても、祀りに参加することのように大事なことなんだと思います。ものづくりをする人も、時にはそういうお互いの力を感じながら作品を作って欲しいですね。
松本 いいお話が聞けました。今日は、ありがとうございました。

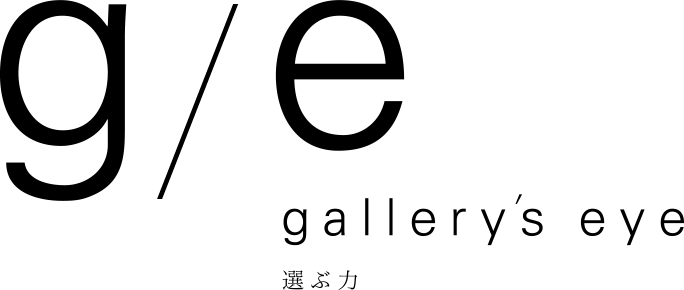











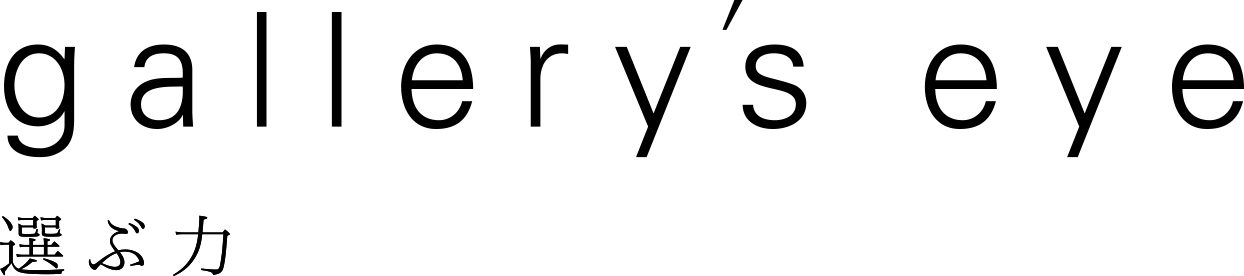


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net