Interview Jikonka 西川弘修 Jikonka / Hironobu NISHIKAWA 聞き手:松本武明(うつわノート) / 文・構成:衣奈彩子 / 写真:大隅圭介 / Oct. 2014
宿場町・関宿の町家を改装して
松本 お店を始めたのはなぜですか?
西川 うちは、家内がもともと陶芸家で、その友人作家たちの作品を集めて販売するようになったのが店を始めたきっかけです。1998年に三重県の松阪市で始めました。そこを拠点に、展示会やイベントに合わせて、津をはじめとした県内のいろいろなところへ出店するうちに、もっと自分たちにしっくりくる場所があるんじゃないかと。三重県には、東海道と伊勢参宮街道があるんですけど、そうした街道沿いの宿場町を探していったら、関という町が環境的に一番良くて。当時の関は、いまのように町を歩く人は少なく、空家もたくさんあったんです。そこで古い町家を見つけました。
松本 それは、いつ頃ですか?
西川 2000年ですね。最初は企画展の時だけ開けて、松阪にも常設店を残して続けていました。
松本 あくまでも三重なんですね。名古屋や京都に行こうというのはなかったですか?
西川 名古屋という選択肢もあったんでしょうけど、そのときすでに子供がいたので、都会に働きにいくイメージはなかったですね。いい店をしていたら、山の中でもお客さんは来るだろうと思っていました。

松本 扱うものは、うつわだけだったんですか。
西川 手織りとか草木染めの服の紹介もしていました。バブル期が終わった頃で、大量消費に対するカウンターという意識はあったと思います。リサイクルとかリユースに興味があって、そういう視点でいいものを長く使うという提案をしたかった。手仕事の作家ものを丁寧に選んで紹介しようという発想ですね。
スターネットが提案するライフスタイルに共感
松本 当時、そのように大都市圏でやらないという実例はあったんですか?
西川 始めてしばらくして「ギャルリ百草」が雑誌に取り上げられていたのを見ましたが、いろんな意味で勉強させてもらったのは、益子の「スターネット」ですね。初期の頃の土壁の「スターネット」を雑誌で見て、ぜひ見てみたいと足を運びました。益子という土地の特殊性は、もちろんあると思うんですけど、着るものから使うもの、食事までを含めたオーガニックなライフスタイルを、地方で、あそこまで徹底して紹介しているのを見て、すごい仕事をしているなと感心しました。
松本 地方でギャラリーを運営するというイメージは、一貫してあったんですね。
西川 地方の人間が東京に店を出すというのは、物価も地価もふくめて、想像以上にハードルの高いことなんです。うちのような個人の会社は、経営のノウハウも資本力もない。大規模なところは、デパートや商業施設に展開できますけど、個人では限界があります。
松本 でも、当時、うつわや手織りの服を買う人と言ったら、都市にいる比較的生活意識の高い人たちだったんじゃないですか。そういう購買層を狙おうと思うと、都市に出店という考えも浮かびそうですが、関でやっても違和感はなかったんですね。
西川 全国のお客さんをターゲットにするというのは、考えていませんでした。当時、こういうお店は珍しかったので、もともといた三重のお客さんに加えて、名古屋や関西からならお客さんが来るんじゃないかと想定していました。むしろいまのほうが、お店も作家も増えて、わざわざ遠くまで足を運んでもらうのは難しいかも知れないですね。

松本 生計は、成り立っていたんですか?
西川 なんとか回っているというくらいの感覚でしたね。僕は、将来的には、自給自足に近い暮らしをしたいと思っていたので、10年くらいの間に、家内が一人で回せる程度の業態で、店のシステムを整えられれば、後は自分のやりたいことができるなと思っていました。
松本 骨董も早いうちから扱っていましたよね。
西川 骨董は、たまたまですね。三重県で草盆栽(松などメインの盆栽の脇に置く草ものの盆栽)を作る人に出会って、そのための植木鉢をオリジナルで作っていました。そしたらほどなくして、盆栽ブームがやってきて、植木鉢を売るつもりが盆栽ごと売ることが多くなったんです。そうなると、今度は盆栽を置く台が必要になって、古道具や古家具から始まって、骨董を勉強したり買い付けるようになりました。すると、世の中が昭和レトロブームに。たまたま早くから古いものをやっていたので取り上げてもらうこともありました。どれも、派生的に広がっていったんです。

大切にしたいのは、衣食住の大切さ
松本 いまでこそ、作家もののうつわから天然素材の服、古いもの、食材までを総合的に提案するお店は一般的ですが、そういう意味では、西川さんは先駆け的存在ですよね。
西川 衣食住の提案をしたいと、常に思っています。何のために、何を食べて、何を使って、何を着るかということですね。うつわを売るにしても、一番大事にしているのは、むしろ食なんです。まずは何を食べるかが重要。
松本 それで、カフェも作ったと?
西川
どういう空間でどう食べるかということに関心がありました。「スターネット」で食事をして美味しいと感じた時に、それはなぜかと考えたら、食材の良さはもちろんですが、うつわがよくて、土壁のある気持ちのいい空間で食べたことも大きな理由だということに気が付いたんです。それまでの日本では、マクロビオティックや玄米菜食というのは、ストイックな世界で、アトピーなど体にトラブルがある人が食べるものというイメージでした。そんな中で、一般の人が普通に美味しく感じ、オーガニックな食事に親しむにはどうすればいいかを考えたくて、カフェを開きました。ギャラリーを始めて3年後の2003年ですね。田舎まで訪ねて来てもらったお客さんに、休んでもらう場所にもなりました。
当時、親が家で料理をしないという傾向が騒がれていたのも気になりました。子供がいるとただ料理するだけでも大変です。でも、おいしい有機野菜を食べる経験や、気に入ったうつわを見つけられる場所という、ある意味、カジュアルでおしゃれなきっかけをうちの店で作って行けば、食べることの大切さがもっと多くの人に響くのではないかと思ったんです。だから、メニューは、ずいぶん工夫しましたね。当時は、玄米ご飯に抵抗のある人が多かったので五分付き米にしたり、豆乳が苦手な人もいるので乳製品は使っていこうとか、そういう風に調整しながらこれまで続けて来ました。

松本 商材として、衣食住のものを選んでいったというよりも、生活の提案がまずあって、その中にそれぞれがあったんですね。
西川 はい。伝えたいのは、衣食住の大切さです。震災以降は、暮らしを見直される方も増えましたが、その1年前にオーガニックマーケットも始めました。誰が作っているのか生産者が分かる有機野菜を販売し、お客さんがそれを選んで消費することによって、生産者を応援することができる。オーガニックマーケットだと、その繋がりがお客さんにも無理なく伝わり安心して買えますね。それを見て儲かるビジネスだと分かれば、必ず真似する人が出て来ますよね。有機栽培に関わる人が増えれば、必然的に環境も良くなる。そういう仕組みができればいいと思っていました。工芸についても、消費者がきちんと選び買うことによって、作家を応援し、工芸が次の世代に残っていく仕組みを作れればいいですよね。
人々の行動や思考の道筋をディレクションする
松本 西川さんは、人の行動や思考の道筋をディレクションしているというわけですね。当時は、それぞれのものがうまく繋がっていないイメージがあったんですか?
西川 そうですね。工芸というのも一部の人の趣味で、オーガニックな食事もある一部の人が必要に応じて取り入れたものでしかなかった。コアな人だけを対象にしたものは、なかなか繋がっていかないので、その間口をちょっとだけ広げたいというのがありました。必要に迫られ、ストイックに取り組んでいる方に叱られることもありましたけど、うちは、オーガニックレストランとうたっているわけではなく、カフェでしたので、カジュアルにいこうと。あれはだめ、これもだめと言っているだけでは、繋がっていかないですからね。
松本 物販をやっている意識は、あまり強くないのでしょうか。
西川
実際に、工芸も服もやっていますから意識はありますが、トータルで提案したいですね。
でも最近は、そういうお店も作家も増えて来たので、売るのが難しくなってきたのは事実です。宣伝にお金をかけたり、イベントを絡めたりということが多いようですが、そこには、ちょっとしたズレを感じています。長く使えるもの、つまり、たくさん売らなくてもいいものを扱っていたはずなのに、どうしてだろうと思うことはありますね。
松本 始めた頃の取扱い作家というのは?
西川 最初の企画展が、黒田泰蔵さん、故・青木亮さん、内田鋼一さん、あとは、西田潤さんという若くして亡くなられた京都の作家さんもいました。当時は、いまほど白いうつわがなかったので、粉引きと白磁をまぜて「白いうつわ展」をやりました。当時の三重のお客さんからみたら、これはこれから絵付けする焼物なのか? 伊賀焼でも万古焼でもなさそうだけど何焼なんですか?という質問もあったくらいで、彼らの作品は、とても新しかったんです。そういうところからスタートして、このうつわは、こう使うとこんな風に育ちますよというようなことを説明しながら提案していきました。

松本 企画展が中心でしたか?
西川 松阪を残して常設をしていたので、関では、2~3年は企画展だけでした。最終的に関だけになって常設展と企画展を交互にやっていましたが、カフェを始めるまでは、あまり人が来なくて週休4日くらいの感覚でしたよ。
松本 売れなくてもいいものを売っていたはずなのにというのは、展覧会をしてたくさん売るというより、そういう作家がいることを伝えたいという気持ちですか?取り扱ってきた作家には、額賀章夫さん、村木雄児さんもいらして、錚々たるメンバーですよね。
西川 家内と作家さんの交流の中から付き合いが始まっているので、同じくらいの年齢やキャリアの人になっていますけど、いまでもいい仕事されている方ばかりですよね。そういういい仕事を紹介して、気に入ったら買ってくださいというスタンスです。
常設展を充実させたい
松本 人気作家ばかりですから、さらに作家を増やしてうつわブームを牽引したり、売上げを拡大することもできる立場にあったと思います。でも、そういう流れは作らず、作家さんとの付き合いを深めていったんですね。
西川
自分たちのお客さんの数と提案するうつわの量を見れば、できることは限られています。だから、どんどん作家を増やすとか、意に添わないものを扱うというのはなかったですね。それがポリシーだったかもしれません。始めた当時は、東京で取扱いがあるのは関東の作家が中心で、関西の作家はあまり知られていなかったと思います。そういうまだ紹介されていない作家のところを訪ねて、話しをして、ほぼ買い取りで譲り受けて販売していたんです。同じ作家さんのものでも、僕が好きなものとそうではないものがあるので、うちに置きたいものを選ばせてもらって常設をしていました。
企画展を繰り返すうちに、作家さんが忙しくなって、納品が少なくなったり、クオリティにばらつきが出るようになったので、個展をするようになりました。でも村木さんの「100碗展」をしたときは、全部買い取ったものでしたね。それ以前に3~4年かけて、窯出しの度に村木さんのところに通い買い貯めていたものを並べました。その後も何年か買い貯めて、世田谷にある東京店で始めて開催した個展も村木さんでした。できれば、ずっと常設をしていたいんですよね。例えば、お茶碗が割れてしまったから、またJikonkaに行って買おうというお客さんもいると思うんです。うつわも服もそうですが、あくまでも日常のものを売るギャラリーなので、常設を充実させたいですね。

松本 最近は、常設を減らして、個展を中心にやるギャラリーが多いですよ。
西川
うちは、四店舗あって人件費がかかるので、個人のギャラリーのようにやってもうまくいきません。自分自身もこだわる部分がありますし。若い作家さんのある作品をいいなと思っても、他はまだかなと思うと個展はできません。若い作り手は、とにかく発表して生活をしたいから、平均的なクオリティが及ばなくても、お店ごとの要望に合わせて納品していくんですよね。うちは、全体のレベルが一定のところまで上がらないと個展はしないので、その頃には知名度も上がって、うちで紹介する意味も機会もなくなってしまうんです。
それよりも、好きな作品を常設していきたい。経営的には簡単ではないですけど、それをしないとギャラリーの眼も育たないですよね。僕らは、作家さんの作品を買い取ってそれを売らないと生活できないというところからギャラリーを始めているわけです。作家が送って来たものを展示して、売れなかったら返しますということをやっていては、作家にだけリスクがあって、ギャラリーはリスクを背負わないことになります。それはできないですね。
海外出店への道筋
松本 暮らし全体を提案するスタイルが関で確立した後、益子のスターネット、東京、台北に販路を広げたのはどうしてですか?
西川 日本の生活雑貨が国内で売れているのは分かっていたので、今度は、もっと海外の人にも見てもらいたいと思うようになったんです。クオリティが高い日本の工芸を紹介するなら、京都がいいとぼんやりと考えていたんですね。それで、京都で物件を探したんですがなかなか見つからなくて。関のような町家とは違う空間がいいと思っていたところに「スターネット」の馬場さんから、一緒に仕事をしないかというお話をいただきました。「スターネット」の店舗内に、販売するスペースをもらうことになって、関と益子を行ったり来たりする生活が始まりました。そうこうしているうちに、東京にいまの物件をたまたま見つけて、関と益子の間で場所もいいし、家内が本格的に制作を始めていた服のアンテナショップとしてもいいということで、東京店をオープンしました。スターネットは、2005年から。東京は、2010年からです。

松本 関から離れ、スターネットで販売することを経験して、ついに東京へ。
西川 はい。自分の手で作った空間で自分が選んだものを売るのとは違い、スターネットでは、お店の人を信じて販売してもらうという経験をしました。東京では、空間作りはできるだけ自分でしますが、売るということに関しては、スタッフを雇い任せるというスタイルを取っています。ひとりでやれることは限られているので、だんだんと任せていくようになりました。そして、第三段階として台北でのビジネスがスタートしました。海外の信頼する人に、自分が選んだものを預けて販売してもらうというやり方ですね。
松本 台北への出店を決めた理由は?
西川 東京店ができた翌年に震災がありました。益子も大変な被害を受けていたので、いろいろな不安はありましたが、関があったからリスクヘッジができて、多店舗を持つことのメリットも感じることができました。そんな中、日本のものを外国の人に見てもらうやり方として、海外に出店するというのもいいのではないかと思っていたところ、いいご縁があって。実際には台湾とのつながりは10年以上になります。親日的ですし、中国茶の文化があり、人々がうつわや工芸に興味を持っているのを感じていましたので出店を決めました。機会があれば、ヨーロッパやアメリカでもやりたいと思っています。

日本の工芸や食文化を海外へ
西川 農産物を扱っていると、行政から知恵を貸してくれと相談を受けることがありますが、国内の限られた消費のパイを、各都道府県で取り合っている気がするんです。もっと、台湾や香港などに販路をのばしていけばいいと僕は思うんですが、国内向けと海外向けでは、行政の担当者が違うので、なかなかうまく繋がらない。農産物や工芸品は、政府のクールジャパン機構が提案するもの以外にもたくさんあるので、もっと海外に出していくべきです。その一端を僕が担えるのならば、積極的にやっていきたいですね。
松本 では、昨今の日本の市場や、作家、ギャラリーやお店に関してどう思ってますか?
西川
クラフトフェアはあまり行かないですし、お店も見ないし、雑誌も読まないです。お店も作家も増えたのは分かるので、お客さんは増えているんだろうなと感じますが、うちにはそんなに増えていないので、実感はありません。ただ、ひとつ感じることは、いまは古典に学ぶというような作家さんが少ないですね。実は、うちで古いものを紹介し始めた理由のひとつに、作家さんに見てもらいたいというのがあったんです。陶片ひとつでも研究材料にして欲しいと思って信楽や常滑から集めて来ると、作家さんがやってきて話が弾みました。いまの作家さんは、違うところで違う情報を得ているのか、デザイン性の高いものを作っていると必要がないのか。残念ですね。いまみたいに工芸品がたくさんある中で、僕が付き合ってきた研究熱心な作家のものが売れなくなるならば、台湾でもどこでも売れるところに行って、人に届けたいと思いますね。

無印良品が家まで建てたり、イケアの家具が人気だという時代ですから、そういう暮らしの中に、ビロード釉がかかった焼き締めなんていうのは、なかなか入っていかないのが現実ですよね。これは、ギャラリーが時代を読み違えたという範疇のことではないと思うんです。東京店では、華道家の先生に教室をしてもらっていますが、習っても家に帰れば花器を置く場所がないんですよね。そういう環境であれば、花を活ける文化もいずれなくなってしまう。壷を置く場所がなければ、壷を作る人はいなくなります。そういう日本で、僕がなにかやってもそう変わらないでしょう。だけど台湾だったら、生活空間も日本より大きく、作家に壷を作ってもらって提案することができます。もちろん、食生活の違いから、売れるうつわの形は異なりますから、どこに届けるかまで考えて作っていかないと。作りたいものを作っているだけでは、売れない時代に来ていると実感しています。そういう意味では、ものづくりの幅を提案したいですね。
暮らしブームのただ中で
松本 高度成長期の大量消費に対して一定の違和感がある中で、日本の暮らしの在り方を探ってきた西川さんは、いいものを選んでいけば、精神的に豊かな調和型の社会ができるということを実践してきた方だと思うんですが、いまは、ある意味それが商品化されスタイルになっています。そういう中で、西川さんが当初抱いていたような思想が引き継がれていないという現状もあると思うんですが、それをどう捉えていますか?
西川 ビジネスですから、儲かるとなれば、真似する人は出てきます。個人のお店がこつこつと時間をかけて提案してきたものを、ある日、大手が真似をして大きく展開してしまうのは、ちょっとずるいなあと思いますが仕方がないですね。市場原理なので、誰にも止められません。でも、スタイルやブームだからと商品を並べているお店は、一過性のものだと思うんです。それに流されず、ある規模を保ってきちんとしたものを作っていれば、理解してくれるマーケットは必ずある。継続していくことが大切というのもJikonkaのポリシーです。僕は、ブームに流されるのも乗るのも得意じゃないので、ずっと普遍的なものを扱っているつもりですよ。

松本 これから、やっていきたいことはありますか?
西川 工芸を提案しつつ、有機野菜や食品をもっと販売していきたいですね。近日中に、Jikonkaのブランドで全国への食品の販売が始まるんです。安心できる食品は、多く流通させてもメリットがあるものだと思っています。
gallery’s eyeに期待する事
松本 Jikonkaは、ギャラリーという概念で捉えないほうがいいのかも知れませんが、今回、gallery’s eyeに賛同したポイントは?
西川 ギャラリーの眼を明らかにするといういいチャンスをいただいたので、僕ができることがあるならやろうということですね。一回のイベントですぐに効果があるものではないかも知れませんが、やり続けていれば何かしらの反応が返ってくるでしょう。影響力のあるイベントになるといいと思います。

松本 選ぶ力や選ぶ眼を意識してやっているギャラリーやお店というのは、文化を創造するということまで考えていると僕は思うんです。
西川 いまは、メディアが作家を取り上げることも多く、作家が直接言葉を発する時代ですよね。その中で、作家と消費者の間に入るギャラリーにどれだけ興味が集まるか、気になります。
松本 そうですね。立地が良くて、洗練された商品をタイミングよく紹介する店というのが、お客さんにとってはいいお店として映ることもあるでしょう。でも、そのお店の起点を作った別のお店というのが絶対にあるはずなんです。うまく回している人の背後には、それを最初に始めて続けて来た人がいる。僕は、そういう道を作って来た人や新たに作ろうとしている人をもういちど見つめることが大切だと思っています。gallery’s eyeを通して、ギャラリーの皆さんの声を聞く事で、混在したお店とものを一度整理すると、その水面下で脈々と続いて来たきちんとした流れが見えてくると思うんです。これからお店をやりたい人にも、ぜひそこに触れて思想があることが大切なんだということを感じて欲しいと思います。西川さん、今日は、ありがとうございました。

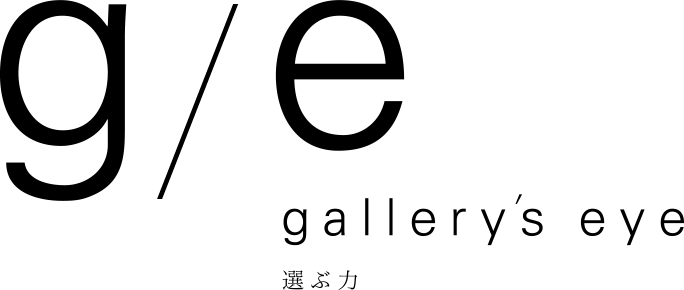











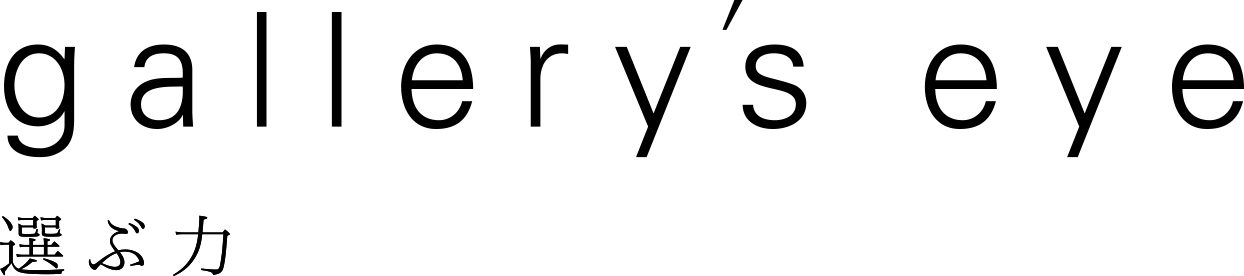


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net