Interview うつわノート 松本武明 Utsuwa Note / Takeaki MATSUMOTO 聞き手:広瀬一郎(桃居) / 文・構成:衣奈彩子 / 写真:大隅圭介 / Oct. 2014
会社員時代にうつわに出合って
広瀬 私は、まず、松本さんが若い頃どういうイメージをもって将来を考えていたかに、とても興味があるんですけれども。
松本 僕は子どもの頃から絵が好きで、美大に行こうと思っていたんです。そして東京の美大に入りデザインを学びました。大学では陶芸も授業で少しだけやったことがありますが、専門課程ではインテリアデザインを専攻し、卒業後は、企業に就職してデザインの仕事をしていました。
広瀬 会社にいた頃から、工芸に興味があったんですか?
松本 いえ、ほとんど。会社員時代はとにかく仕事ばかりで、大した趣味もありませんでした。最初はメーカーの宣伝部に13年。その後インターネットの黎明期に通信会社に転職をして13年。宣伝、デザイン、イベント、インターネット企画などマーケティングに近い分野の仕事に長く携わってきました。
広瀬 転職してさらに忙しい時期が続くわけですか。そんな超多忙な人生のなかで、なにゆえ工芸、しかもうつわなんていう時間に余裕のある人が好むようなものに?
松本 僕が、うつわに出合ったのは2004年。まだ10年も経っていないんです。40歳を超えて仕事がマネジメントの立場になり、定時に帰れる事も多くなったので陶芸教室に通い始めたんです。そこで、自分で作るための参考にうつわを見始めたのが最初です。その頃は、うつわ店で作家ものの粉引の飯碗ばかりを購入していましたね。作り手の人と話すうちに、この時代にこんなに不器用というか、シンプルでまっすぐな生活している人がいるんだということを知りました。とくに僕が出会った陶芸家というのは、有名になりたいという訳ではなく、自分の作るものと自分の暮らしとのバランスを取りたいという人が多くて。その作品は、抑制的で自己主張が少なくて野にひっそりと咲く美しい花のようでした。

ブログ・うつわノートをスタートする
松本 僕のように80年代に会社勤めをしていた人間というのは、日本経済がまだ好調な時期でしたから、働くことと経済的なゆとりが比例していて、生活資産を豊かにすることがひとつの指標でした。仕事の性質上、対象となるのはマス・マーケットばかりでしたから人と人の距離で言えばリアリティに欠けるんですね。一方、うつわの世界には、古くからの直接的なマーケットがまだ残っていてリアルな人間関係があった。当時は精神的に辛い事もあって、そんな時にうつわに出合ったので、自分が許されるような気がしたんですね。大げさなことを言うとうつわに命を救われた感じがあって。その世界に自分も参加してみたいという気持ちが芽生えました。
広瀬 うつわノートという、うつわ好きなら誰もが見ているであろうあのブログは、この世界への参加の形として始めたということですか?
松本 そうだと思います。最初は、うつわに関する知識を満たしたいというのもあって、紙のノートに自分で作った陶芸のことや展示会で見たもの、購入したもの、作家さんの経歴について書き留めていました。それを紙で管理するのが大変になってきたので2006年にブログにしたんです。
広瀬 その間も、お勤めはずっと続いていたんですよね。
松本 気持ちは、会社からずいぶん離れていましたけどね。うつわを事業にする自信や知識はなかったですがお店に対する憧れはありました。ギャラリーの方や作家さんとお話をするようになって、決して経済的に潤う世界ではないのも分かったけれど、それでも、精神的にすごく豊かな世界なんだということに気付いたんです。そして、だんだん自分の仕事にしてみたいと思うようになりました。うつわを見始めて4〜5年経った頃には、お店を持つという視点で作家さんやギャラリーの方と話すようになったと思います。

広瀬 準備は、どのように進めたんですか?
松本 いろいろと見たり体験したことを、うつわノートに、とにかくポジティブに書く。頭に蓄積した情報を書き出してみるということがすでに準備期間だったんだと思います。しかし、場所を探したり、作家さんとの取引など具体的な行動に移ったのは、オープンの1〜2年前からです。
広瀬 立地には、いろいろな選択肢があったと思いますけれども、都心部よりも郊外型のゆったりと見てもらえる場所をイメージしていましたか?
松本 東京で長い間、会社勤めをしていて、その環境に失望する事でこちらの世界に惹かれたこともあって東京ではやりたくなかった。東京でやるとついマーケティングの見地から考えてしまって、また同じことになりそうで。そこで伴侶の実家が埼玉ということで、埼玉から探そうと。半年ぐらい探した後に、今の物件に出会って結果的に川越になりました。
うつわが生まれた文化的背景まで掘り下げる
広瀬 ギャラリーのコンセプトは、明確にありましたか?
松本 さほど明確ではなかったですが、ブログで書いて来たことも影響してか、うつわという“もの”だけでなく、その作り手の背景やさらには文化的な接点も含めて伝えたいと思っていました。また自分のギャラリーの存在意義というのも考えたかったですね。うつわをたくさん見て来たので、人気作家も、売れ筋のうつわも大よそ分かっていました。ただ、そういう視点から選択をすると、作家さんの名前だけでお客さんを呼んでくるお店になってしまうので、むしろあまり知られてない方や知られているけど今はきちんと理解されにくい方、そういう作家を紹介することに自分がギャラリーを開設する意義を感じていましたね。問題提起があって、それをどう解決するかというのが自分の役割だと思いました。まだうつわを知らない人にも広く知らしめていく一方で、うまく伝わっていないものは、伝え方を変えてみるということですね。それは思想というよりも、多分自尊心に繋がっているんだと思います。作家さんに褒められたいという気持ちがモチベーションに繋がっているところがある。売上げという指標だけでなく、うつわノートでやってよかったと言われたいということですね。

広瀬 どうやって作り手の魅力を伝えていくか。松本さんが、コンセプトを立ててひとつひとつ丁寧にやっていることは、見ていて強く感じるんですけれども、若くて新しい作り手を見つけてくるというのも、うつわノートの力だと思うんです。この人に展覧会をやってもらいたいという引き金になるのは、どんなことなんでしょうか。
松本 ものの良し悪しや好き嫌いについては、この7〜8年で見て来たものの中で僕なりの基準があります。それに加えて大切なのは、その作家がこちらを必要としてくれているかどうか。自分の役割があると思った時ですね。すごく優れたものを作っているから一方的にお願いしたいとは思わなくて、相手にもこちらを必要として欲しい。やるからには、良いところをどれだけ抽出して表現するかということに努めますね。それがお店の役割だと思っているし、どの作家にも生活がかかっていますから、有名だろうが、そうでなかろうが、同じだけの力は懸けていきたい。その上で結果に差が出るのは仕方がないという考えでやっています。
広瀬 テーマやコンセプトに沿ったもののラインナップは、松本さんが考えるんですか?
松本 人に依ります。すでにテーマを持って制作している作家さんの場合は、その人が作るいまのものをどう表現するか、表現者の方に回ります。一方で、まだ手探りの作家さんについては、どういうところに強弱をつけてテーマ設定をするか、編集が必要ですね。お客さんというのは、最初からその作家のもののすべてを理解できる訳ではないので、理解し易いところを取り上げて強調するという作業をします。具体的なテーマを立てて制作物に反映して欲しいとお願いすることもありますし、テーマに添った資料をこちらで集めて提供し、そこに絞って作ってもらうということもあります。ただ、いずれも話し合い次第なのでこちらが一方的に仕切ることはないですね。最終的に何を選ぶかというのは、作家さんにお任せしています。



広瀬 新しい作り手と出会っていく“うつわノート方式”みたいなものはあるんでしょうか。ギャラリーを始めてからは、クラフトフェアに足を運ぶのも難しいのかなと。
松本 以前はクラフトフェアもひとつの選択肢でしたが、いまは気持ちが離れています。むしろいい作家の周辺には、いい作家がいて、人と人で繋がることが多いですね。とにかく会ってみるのが大事。肝心なのは、未完成であっても良いところを見逃さない眼が大切だと思っています。
広瀬 ギャラリストになってからと、それ以前では、工芸に対する見方に変化はありますか?
松本 うつわを見始めた頃というのは、自分も精神的に傷ついていて、うつわの世界に救われたという自覚があったから、何に対しても謙虚だったんです。この世界の仲間にいれて欲しいと思っていたので。お店を始めてからは少し自我が芽生えてきて、また作家さんへの責任も生まれるので、一方的にへりくだるだけでは成立しないなと感じていますね。最近は、流行に対して疑問を投げ掛けたり、作家さんに対して意見することも良くありますから、もしかしたらブログだけの頃に比べて変わったなと思っている人もいるかもしれません。
gallery’s eyeを仕掛けた理由
広瀬 生活工芸を取り巻く環境について、松本さんの意見を聞いてみたいんですけれども。
松本 自分が見てきたのは、まさに生活工芸の領域のものばかりでした。美術工芸やお茶道具には、リアリティがなかったし、関心が沸かなかった。「桃居」さんや「うつわ楓」さんを始め、たくさんのお店で今の暮らしに沿ったうつわを見て来ました。また、右肩上がりだった日本の経済が90年代に止まって市場が落ち込むところも企業で経験してきた。そういう中で、日本人が経済という尺度とは別の方向で豊かな生活を選択する、つまり、もう少し自分達の足元を見つめて、長く使えるものを選ぶとか、安全なものを食べるという方向に向かってバランスを取り始めたのを感じて来ました。北欧のような文化的成熟に社会が向いてきたような気がするんです。僕が生活工芸の領域に魅せられたのも、経済成長とは違うところに人が求める最終地点があるということに共感したからだと思うんですね。
広瀬 なるほど。
松本 ただ、自分がこのフィールドで仕事をするようになって感じるのは、この領域がひとつの流行やスタイルになってきて、ムードに流され過ぎているんじゃないかという危機感があるんです。最近は、程良いセンスの作品が、生活工芸というブームに乗って生まれて、そのスタイルだけで消費されてしまう。僕は、茶の湯や美術工芸の世界をいままでは否定的に見て来たんだけれども、そういう工芸が培ってきた歴史や骨格にも繋がっていないと、モノの本質が失われるんじゃないかなと思うようになって。そこで敢えて憎まれ役を買って出る覚悟で、このイベントを通じて、このままじゃいけないんじゃないの?というのを言葉にしようとしています。
広瀬 うつわノートがオープンした2011年頃に、焼物の根っこにある骨っぽさをきちんと伝えるお店が新規に立ち上がるのは珍しくて、生活道具と作家の作品、生活道具と骨董を一緒に紹介したり、カフェを併設したりするライフスタイルショップが多かった気がするんですよね。そういう流れにくさびを打つような形で出てきたお店だったと思います。今回、gallery’s eyeで、10軒のお店が自分たちなりのポジションをきちんと主張するという試みを仕掛けたのは、ライフスタイルショップが全盛の時代に対するアンチテーゼなんですか?
松本 クラフトフェアやライフスタイルショップが増えて、心地よくて暮らしに寄り添ううつわという言葉が全盛になっていると思うんですね。その謙虚な美しさは自分も好きだけれども、その価値基準ばかりになると、マーケットには、技術や思想を語らないものだけが並んでいく。そういう軽やかな工芸と美術工芸のマーケットが、今は完全に分離していると思うんです。僕は、その間をもっと多層化するべきだと思っていて。例えば、生活寄りなんだけれども、もっと技を強調したものとか、もっと古典的なものとか。いまの作り手の中には、土から自分で掘ってきて粘土や釉薬を作り、原始的な薪の窯で焼く人もいる。そういう時間と労力をかけて作っている人が、今の市場にそぐわないために評価されない。でも作りたいのは生活の道具であって、茶陶や美術工芸ではないとなった時に、その間を引き受けるギャラリーも必要だと思っています。たとえ、いま売りづらくとも、それをきちんと伝える姿勢が大切だと思います。



広瀬 真ん中が抜けている状況があるというのは、確かですね。作り手に関して言えば、決してライフスタイルに寄り添うものだけを作る人ばかりではないと思うんです。むしろ、ショップやギャラリーというのが、繋ぎ手としての使命を持ってやるべきなのかなという気がしますよね。
松本 昔は、作家さんがお店に鍛えられるとか、お店もお客さんに鍛えられるとか、お互いが切磋琢磨する中で作られたものも多いと思うんです。いまは、作り手と買い手が友達のような関係で成立している共同体のような気がするんですよね。
広瀬 居心地がいいといえば、いい世界なのかもしれない。
松本 でも、ものを作るっていうのは、もっと泥臭くて葛藤があって、問題意識もあって。そういうゆがんだ部分から生み出されるものの強さってあると思うんです。もっとそういうところにも目を向けていきたいと思っています。
商う人にも選ぶ人にも、もっと多様性があっていい
松本 さらに、そういう根っこがあるものを大切にしながら、多様性も重視したいと思っています。うつわノートは、プロダクトデザイナーが関わっているものや、オブジェやファニーな陶器、彫像も紹介する。いろいろな選択肢があることが、市場として豊かだと思っているんです。
広瀬 そうですね。うつわノートのラインナップを見ていて思うのは、生活的な工芸をベースにしながらも、さまざまな可能性を見ているというか。これからは、さまざまなレイヤーに分かれたさまざまな作り手が、平行してものを作っていくという意味で豊かな時代だと思うんです。僕は、作り手には、ものすごく豊かな可能性を感じているんだけれども、商い手とか繋ぎ手に関しては、厳しく見てしまうところもあって、もう少し、さまざまな形態があってもいい。そこが、弱くなっているんじゃないかと感じますね。ライフスタイルショップが悪いわけではないけれど、あまりにも乱立して飽和しきっているし、そういう状況に違和感を覚えている若い人も多いと思うんです。でもどんな時代も、振り子が振り切れると必ず揺り戻しがあるものなので、若い人の中から、新しい、いままでになかったようなギャラリーやショップを試みたいという人が出てくる予感がするんですけれどもね。
松本 商う人、選ぶ人にも、もっと多様性があっていいですよね。
広瀬 そうですね。gallery’s eyeは、作り手、使い手、商い手の3方向に発信すべき場所。作家に対して自分たちの思いを伝え、お客様にも発信するんだけれども、もうひとつの目的として、これからギャラリーを始めたい人、そういう志を持っている人に対して、刺激をあたえて触発できる場にしたいですね。
うつわを買うことは、自分の意識を育てること
広瀬 うつわノートの今後をどう考えていますか?
松本 一番の目標は、続けることですね。単発の面白い企画をやる事は出来るかもしれないけれども、雨の日も風の日も何年も続けていくというのは、なかなか出来ないなあと。うつわ屋というのは、お客さんとも作家さんとも付き合いが長くなるものですし、お店に来るという体験もふくめて提供している。インターネットを通してものを買うということが一般化しているけれど、リアルに顔を向き合わせる形でものを買うコミュニケーションというのは、これから大切だと思うんです。うちは川越の駅から離れているところでやっていますが、それでもお客さんが来てくれるんですよね。ありがたいと思うと同時に、そこまでして選んで欲しいなっていう気もするんです。同じものでも、体験というものが付加されると、意味が違うんじゃないかなって。とくに、生活工芸の場合は、買ったものを暮らしの中に持ち帰ってそこからまた物語が生まれていく。我々が売っているのは、ものなんだけれども、ストーリーも含めたものにまつわるさまざまな事柄なんだという意識はありますね。
広瀬 ある意味で、買う側もクリエーションしているんだと思いますよ。選んで対価を払って自分のものにするっていうのは、消費なんだけれどもある種のクリエーションでもあるっていう。
松本 うつわって食の道具ではあるんだけど、見惚れている部分は、もっと情緒性だと思うんです。自分の生活を愛でることに対する投資だと思うので。無駄な部分に感情移入して、苦労して所有するっていうのは、醍醐味なんじゃないかな。そういうところが楽しいんだと思いますね。
広瀬 うつわについていうと、自分の食器棚というある種のワードローブがあって、そのワードローブの中をどういう風に組み立てていくかという楽しみでもありますよね。そういう意味では、間違いなくクリエーション。創造的な行為ですよね。若い人も含めて、食器がこれまで連綿と買われて来た歴史があるというのは、その楽しさなんだと思います。
松本 「物買って来る、自分買って来る」という河井寛次郎の言葉がありますけど、結果的に自分の意識を育てている行為なのかもしれないですね。自分に返ってくるというか。機能的な美しさが重要視されがちですけど、用途だけで言ったら、量産のもののほうが優れている場合もあります。でもそうじゃないものを選ぶということは、もうちょっと情緒的なものを求めて選んでいるんだと思うんです。そういう感情に素直になるなら、表現主義的なものや、抽象的なアートを自分の空間に置くのもいいと思いますね。そこに興味があるお客さんは、実際に増えていると思います。 うつわノートの場合は、これから古典的なものもお店の中に取り入れて、“新保守”の視点から、もっと新たな提案をしてみたいと思っています。

広瀬 今日はありがとうございました。

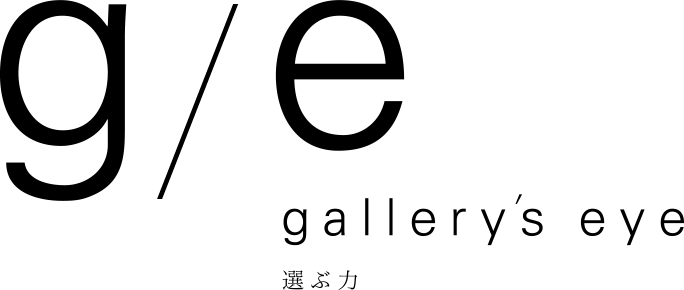











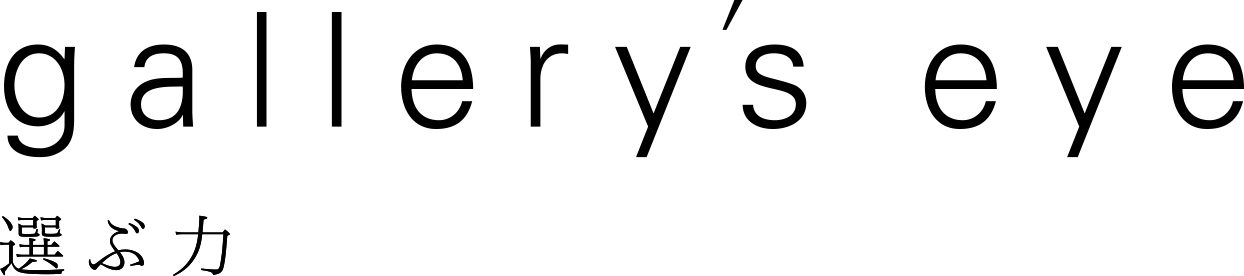


 https://panorama-index.jp
https://panorama-index.jp https://filament-jp.net
https://filament-jp.net